�@�@�c��`�m�@�֎�
�@![�O�c�]�_](img/def/title.gif)
�@�@����31�N3���n���i����1��1�����s�j
�@�@ ���s�F�c��`�m�@�ҏW�l�F�c��`�m�L���@�ҏW�E����F�c��`�m��w�o�ʼn�
|
|
 |
2018�N6�����\�� |
|
       ![�O�c�]�_�Ƃ�](img/def/menu/off_images/menu_bar_08.gif)          |
| |
|
|
| �����P��P�����s |
| �ō����i�F451�~�i�{�� 410�~�j |
| ����w�ǁF4,700�~�i�ŁE�������j |
| �ɂȂ� |
 |
 |
|
 |
|
| |
| �����W |
|
��N�Ă̓����ł̃f���O�M�̔����A�܂����A�t���J�ł̍�N���̃G�{���o���M�̗��s�̓j���[�X�ƂȂ�܂����B�l�ނ̗��j�͊����ǂƂ̓����̗��j�ł���A���ł����ݎO�労���ǂƌĂ��A���j�A�}�����A�A�G�C�Y�́A���E�Ŋ����҂����N�����������A�����̕����S���Ȃ��Ă��܂��B���{�͊����ǐ����Ŗڊo�܂������ʂ������A���ۓI�Ɋ��҂���鑶�݂ł����A���݂̃O���[�o�������ǂ͂ǂ̂悤�ȏȂ̂ł��傤���B |
| |
| �q���k��r�����Ǒ�ɋ��߂�����{�̍v�� |
| |
�������j�i���v���c�@�l�G�C�Y�\�h���c��\�����j
����B�j�i�m�o�n�@�l�}�����A�E�m�[���A�E�W���p���ꖱ�����������ǒ��j
�R�{���Y�i�����w�M�ш�w���������ەی��w���싳���j
���g�@�i�Ɨ��s���@�l�n���Ë@�\���i�@�\�������E���I�m���j
���q���G�i�c��`�m��w�Ō��Êw���E��w�@���N�}�l�W�����g�����ȋ����i�i��j�j
|
|
| |
| �q�֘A�L���r |
�v�g�n�ɂ�����O���[�o�������Ǒ�ƌc��`�m�ւ̊���
���J��C���i���E�ی��@�ցi�v�g�n�j�����ǒ���E�m���j
|
| |
����̊����ǂ̓����Ƒ�
��c�@�q�i�c��`�m��w��w�������NJw���������A����w�a�@��������Z���^�[���j
|
| |
| |
|
|
|
|
| �@�c��`�m�ێ��� |
��Z���v���m���ƓĎu�Ƃ̊F�l�ɂ��A�`�m�̋��猤�������������x������ړI�Őݗ����ꂽ�ꐢ�I�]�̗��j��L����g�D�ł��B
����̊F�l�ɂ͂��������ԁw�O�c�]�_�x�悢�����܂��B |
|
|
| |
|
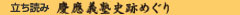 |
|
�O�c�L�����p�X�̐��Z�ɂ̂���R��ɁA�I��܂ł́A�u��u���v�A�܂��́u��z�[���v�ƌĂ�Ă����������������B�c
|
|
|
|
|
 |
|
|
| �����̑��̊�� |
| ���b��̐l�� |
| �O���[�o���ʐM��Ƃ̃g�b�v�Ƃ��� |
| |
|
 |
�g�c���T����@
�i�a�s�W���p��������Б�\������В��E�m���j |
| |
�C���^�r���A�[
�H�c����i�c��`�m��w���H�w�������j |
| |
|
| ���E�I�ȒʐM�C���t�����x�����Ƃ̃g�b�v�߂�g�c����́A���̂قǏ����Ƃ��ď��߂ĂƂȂ�o�c�A�����A�C�����肵�܂����B�C���^�[�l�b�g���͂��߁A���⎄�����̐����ɕs���ȒʐM�C���t����S����Ƃɋ��߂�����̂Ƃ́B�܂��A�O���[�o���ȕ���œ��{�l�A���{��Ƃ�����ɂ͂ǂ�Ȃ��Ƃ��K�v���B�M�ӂ��ӂ��C���^�r���[�ł��B |
| |
|
 |
| �����߂Ĉ��ܔN�O�̂���Ʉ����n�[�o�[�h��w�K�⁄ |
���Ɓ@�āi�c��`�m���j
|
|
| ���O�l�Ւk�� |
| �u�W���Y�i���v�ŃX�E�B���O |
�c��r��Y�i�����{�V���Ћq���ҏW�ψ��E�m���j
�V���[�g�E�A���[�i���}�n������ЋΖ��E�m���j
���새�E�i���y�]�_�ƁA�c��`�m��w��w�@����E���f�B�A�����ȓ��C�y�����j |
|
| 60�`70�N��ɂ����ė������ɂ߂��u�W���Y�i���v�B���{�Ɠ��̃W���Y�����Ƃ��Ēm���Ă��܂����A�Ⴂ����ɂƂ��Ă͏����~���������ꏊ��������܂���B�����������̃W���Y�i���Ƃ͂ǂ�ȋ�ԂȂ̂��B���̓Ɠ��̃��[���Ƃ́B���y�Ƃ̊ւ������傫���ω����Ă��錻�݁A���߂āu�W���Y�i���v�ɂ��Č��s�����܂��B
|
| |
| ���A�ځ� |
| �@KEIO MONO MUSEUM70 |
|
| �@���ʕ��u�ژH�͂邩�����v�u�t���� |
����@�R����Y |
�@����ɐ����镟�V�@�g�̂��Ƃ@����100
|
��v�ے��@ |
|
���V�P�� |
|
| �@ |
| �������ف� |
�@�ߑa���E�������n��Ǝ��R�ЊQ
�@�����V�������z�n�k�̋��P���瓾��ꂽ���� |
�V�c��_ |
|
|
|
| |
| ���u���^�� |
| �@ ���Ǝ������킪������ |
�������v |
|
| �����̑��� |
�@�u�̏� |
�q�{d�A����d��A�������q�A�˓c���� |
�@�m���N���X���[�h |
���@�o�A�F�@�m�� |
| �@Researcher's Eye |
�����M��A�䉜�^��A���C�їS�q |
| �@���M�m�[�g |
�w���A�W�A���������n���w�����������{�̖����x
����G�m
�w�����w�E��p�E���ۘA���������c���j�ƐV�n�ˈ�x
���J���ؐl
�w�C���������T�x
�{�Ɓ@��
�w�q�ǂ��̍˔\����ބ������������镟�V�@�g�̎q��ĂƋ���x
�����@�O
|
| �@�������i�p���j |
�����F�q�A�ʓc�֎q�A�n�Ӎ��ށA�Ԗ؊��� |
|
| ���Ǒz�� |
| �@�ъ�j�搶���Â� |
�����S��Y |
| �@�]�₳��𓉂� |
�ߐX�@�� |
|
|
|
|
|
|
|