No.1301(2025年7月号)
特集
No.1301(2025年7月号)
特集

現在国民2人に1人が「がん」にかかると言われています。その一方、早期発見、医療技術の進歩に伴い、以前あったような「死と隣り合わせ」というイメージは薄れ、治療により完治し、またがんと共存しながら社会復帰して生活していくことが多くのケースで可能になっています。そのような現状を踏まえ、就業など社会とのかかわりの中で、今、何が課題となっているのか。がんサバイバーの方からの視点、高額療養費制度をめぐる議論、相談支援センターの役割など、今日的な課題を網羅した特集です。
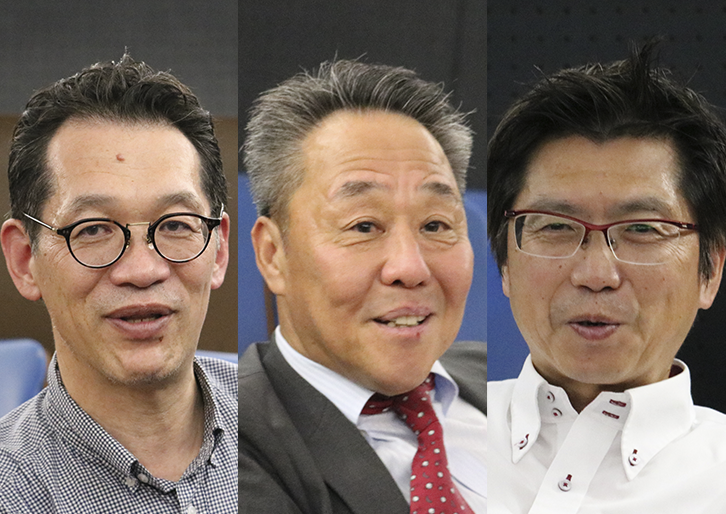
ドイツでの最初の一般公開から100年の節目を迎えたプラネタリウム。日本でも試行錯誤が重ねられ、独自の進化を遂げてきました。近年は子ども向け教育番組から大人も楽しめるヒーリング企画まで、趣向を凝らした鑑賞イベントも目白押し。この夏は涼を求めてプラネタリウムへ星空観賞に出かけてはいかがでしょうか。

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。
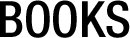 慶應義塾大学関連の書籍
慶應義塾大学関連の書籍