�@�@�c��`�m�@�֎�
�@![�O�c�]�_](img/def/title.gif)
�@�@����31�N3���n���i����1��1�����s�j
�@�@ ���s�F�c��`�m�@�ҏW�l�F�c��`�m�L���@�ҏW�E����F�c��`�m��w�o�ʼn�
|
|
 |
2018�N6�����\�� |
|
       ![�O�c�]�_�Ƃ�](img/def/menu/off_images/menu_bar_08.gif)          |
| |
|
|
| �����P��P�����s |
| �ō����i�F451�~�i�{�� 410�~�j |
| ����w�ǁF4,700�~�i�ŁE�������j |
| �ɂ��� |
 |
 |
|
 |
|
| |
| �����W |
|
�n�挤���Z���^�[�i�����A�W�A�������j���ݗ������30�N�B���̑O�j���܂߂ē��{�̒n�挤���̔��W�Ɍc��`�m�͑傫�ȍv�������Ă��܂����B���_�����ł͕����肦�Ȃ��A�u����v�ɑ���؎��ȃR�~�b�g�����g���玖����������H�̊w�ł���n�挤���̎��_�́A���݂̐��E�g�����h�̗����ɑ傫�Ȏ�����^���܂��B�O���[�o������ɓ������n�挤���̓���Ɩʔ�����`������W�ł��B
|
| |
| |
�q���k��r
�n�挤���̂䂭���������ς��鐢�E�̒��� |
| |
�|����t�i������w�@�w�������j
���c�p�Y�i�c��`�m��w���_�����j
���{�����i�݂��ً�s�O���[�o���g���[�h�t�@�C�i���X�c�ƕ������E�m���j
����T��i�c��`�m��w�@�w�������j
�����L�v�i�c��`�m��w�@�w�������A���A�W�A�����������j
|
|
| |
| �q�֘A�L���r |
| |
��i�����̒n�挤�������I�[�X�g�����A�����̎��_����
�֍������i�c��`�m��w�@�w�������j
|
| |
�n�挤���ƌc��`�m�����l���Љ�Ȋw�̎�������
��ؐ����i�c��`�m��w���w�������A���A�W�A�������������j
|
| |
�c��`�m�̒�����������
�R�c�C�Y�i�c��`�m��w���_�����j
|
| |
|
|
|
|
| �@�c��`�m�ێ��� |
��Z���v���m���ƓĎu�Ƃ̊F�l�ɂ��A�`�m�̋��猤�������������x������ړI�Őݗ����ꂽ�ꐢ�I�]�̗��j��L����g�D�ł��B
����̊F�l�ɂ͂��������ԁw�O�c�]�_�x�悢�����܂��B |
|
|
| |
|
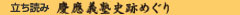 |
|
�u�O�c���w��Ă̐e�v�Ƃ��̂���鐅��둾�Y�A�{�������͑��́A���n���̌c��`�m�Ɋw�сA���{�ōŏ��̐����ی���ЁA����������n�����������ב��̎q�ł���B�c
|
|
|
|
|
 |
|
|
| �����̑��̊�� |
| ���b��̐l�� |
| �����ȃN���j�b�N�����Â�ς��� |
| |
|
 |
������������
�i�s��4�J����365 ���N�����x�̏����ȃN���j�b�N���^�c���E�m���j |
| |
�C���^�r���A�[
��쏮�v�i���������Ì����Z���^�[�E�m���j |
| |
|
| ���݁A�s���S�J���łR�U�T���N�����x�̏����ȃN���j�b�N���^�c���̔�������B���鏬����Â̌���Ɍg���ƂƂ��ɁA���̑g�D�̃}�l�W�����g�ɂ����Ă���������Ă��܂��B�Ⴋ�����Ȉオ�߂������z�̈�ÂƂ́A�����Ă��ꂩ��̈�t�ɋ��߂�����̂Ƃ́B��Â̖��������߂�C���^�r���[�ł��B
|
| |
|
 |
| ���O�l�Ւk�� |
| �����}���K�̔����I |
�����������i����Ɓj
����@�m�i����Д̔���`���E�m���j
�������i�c��`�m��w���w�������j |
|
| �����݂̂Ȃ炸�A�j���ɂ������̃t�@�������u�����}���K�v�Ƃ����W�������B�����A��ڂ����@��̑������́u�����}���K�v�Ƃ́A��̂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤���B�t��������u�Q�S�N�g�v�̎�����o�Ă��܁A�����}���K�͂ǂ��ɂ���̂��B��ƁA�ҏW�ҁA�ǎ҂̗��ꂩ��A���߂Ă��̗��j���Ђ��Ƃ��܂��B |
| |
| ���A�ځ� |
| �@KEIO MONO MUSEUM64 |
|
| �@�Ō�̑��c�� �I��̊������͊� |
����@���R�@�� |
�@����ɐ����镟�V�@�g�̂��Ƃ@����94
|
��v�ے��@ |
|
�R���c�� |
|
| �@ |
| �������ف� |
| �@���ς���C���h�h�s�ƊE |
�����s�Y |
|
|
|
| �����̑��� |
�A�C���V���^�C���́w���̓��{���s�G���x��|��
�֓����Y |
| |
|
�@�u�̏� |
�����N�G�A���쐳�_�A�{���~�i�~ |
�@�m���N���X���[�h |
���V���j�A�ėǂ͂邩 |
| �@Researcher's Eye |
����m�h�A���@��
|
|
|
|
| �@���M�m�[�g |
�w�Ղ͂��Ƃ��܂��@���{�̃r�[���ʔ��q�X�g���[�x
�[�c�@��
�w�j�̃p�X�^���x
�y���@��
�w�H�n���̖��{�����x
�����Y�F�i�Ғ��j
|
|
|
|
|
�@���]
�@ |
�w�`�L����M�O�x�i�_�g�n�j
�с@�]
|
|
|
|
| �@������
�i������ �j |
���я[���A����T���A�_�c�f�q�A���ꔎ��
|
|
|
|
| �@�Ǒz |
���R����搶���ÂԄ����u�ɂ���v�Ɓu�ɂ��v
���J�R��
�I�܂���B���������c�גj�N�Ǔ�
�ѓc�T�N
|
|
|
|
|
|
|
|
|