慶應義塾機関誌
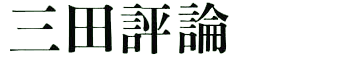
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
| |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
国連をはじめとする国際機関ではたらく日本人は、これまであまり多くありませんでしたが、日本人だから出来る貢献・支援を考え、国際機関を目指す若者は徐々に増えています。国籍にとらわれない考え方が必要である一方、出身国ならではの貢献が求められる、仕事の現場。国際機関ではたらくことの意義や達成感、そして日本人に求められるものについて、世界各地で活躍してきた方々の座談会と関連の記事で理解が深まる特集です。 |
| |
| |
| 〈座談会〉国籍にとらわれず世界の力に |
| |
一盛和世(元世界保健機関(WHO)ジュネーブ本部専門官、長崎大学客員教授)
二井矢洋一(人事院事務総局国際課長・塾員)
大窪直子(国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)職員・塾員)
洪 実(慶應義塾大学医学部坂口光洋記念システム医学講座教授)
菱田公一(慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授)
|
|
| |
| 〈関連記事〉 |
| |
平和構築を仕事として
渡邉真樹子
(世界銀行東アジア・大洋州地域総局マニラ事務所[社会開発専門官]・塾員)
|
| |
国連職員として働くということ──国際社会の平和と安全を求めて
石川直己(国連平和維持活動局政務官・塾員)
|
| |
国際公務員を目指せ
木村福成(慶應義塾大学経済学部教授)
|
| |
|
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
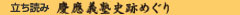 |
|
港北区下田町は、古くは橘樹郡駒ヶ橋村と称した。その名の由来としては、源頼朝がこの村を通過するとき、乗馬が急に走り出してようやく橋の辺りで止まったから、という説がある。明治二十二(一八八九)年に市町村制が施行され、矢上村、南加瀬村、鹿島田村、駒林村、箕輪村、小倉村と合併して日吉村大字駒ヶ橋となった。…
|
|
|
|
| |
| 前号紹介 |
| 2014年2月号 No.1175 |
◆特集◆
自転車と社会
|
 |
| |
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
 |
| <三人閑談> |
| ムーミンの国フィンランド |
末延弘子(フィンランド文学翻訳家)
石崎洋司(児童文学作家・塾員)
矢澤和明(慶應義塾普通部教諭)
|
|
| 今年はムーミンの作者トーベ・ヤンソン生誕100年。世界中に多くのファンがいるムーミンがあらためて注目されています。フィンランドの、強国に挟まれた歴史と厳しい自然のなかで育まれたムーミンの独特の世界観は、子どもはもちろん大人まで魅了してやみません。「ビジネスマンにこそおすすめ」とも言われるムーミンの物語を、この機会に読んでみませんか。 |
| |
| <連載> |
| KEIO MONO MUSEUM58 |
|
| 98式航空エンジン |
解説 澤田達男 |
|
大久保忠宗 |
|
大澤輝嘉 |
|
| |
| <演説館> |
| インターネット時代のコンテンツビジネス |
野副正行 |
|
| <その他> |
丘の上 |
大島通義、萬代 治、水鳥真美、宮坂直孝 |
塾員クロスロード |
山本ゆきの |
| Researcher's Eye |
八木 洋、井関裕靖、小暮厚之
|
| KEIO Report |
慶應発ベンチャー企業、念願の東証上場
冨田 勝
三田評論を速記で支えて四十余年──小島二三子さん
慶應義塾広報室 |
|
|
|
| 執筆ノート |
『今上天皇 つくらざる尊厳──級友が綴る明仁親王』
明石元紹
『国立競技場の100年
──明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ』
後藤健生
『日本教育の根本的変革』
村井 実
『確率の出現』(イアン・ハッキング著)
広田すみれ(共訳)
|
|
|
|
追想
|
やさしさの人、三井宏隆さん
渡辺秀樹
|
|
|
|
| 社中交歓(つくし)
|
長田亘弘、土本寛二、湯木俊治、吉野鉄大
|
|
|
|
|
|
|
|
|