慶應義塾機関誌
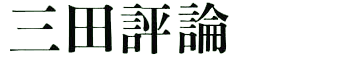
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
この7月の参議院議員選挙で、日本では初めていわゆる「ネット選挙」が解禁となりました。実施される前から様々な変化の予想やそれに期待する声がありましたが、投票率は低迷しました。この選挙を通して明らかになった政治家や有権者のインターネット利用の姿を分析し、より多くの民意を反映させるためネットなどのメディアをどのように活用していくかを問う中で、これからの日本の政治、そして民主主義社会のあり方を考えて行く特集です。 |
| |
| |
| 〈座談会〉メディア政治のなかのネット選挙
|
| |
田中愛治(早稲田大学政治経済学術院教授)
井原康宏(共同通信総務局次長)
西田亮介(立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准教授・塾員)
李洪千(慶應義塾大学総合政策学部専任講師)
大石 裕(慶應義塾大学法学部長、法学部教授)
|
|
| |
| 〈関連記事〉 |
| |
「ネット選挙」の捉え方 ──政治コミュニケーション論から批判的に考える
山腰修三(慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所准教授)
|
| |
ネット選挙の進化は何をもたらすのか ──二〇一二年アメリカ大統領選挙戦を事例に
清原聖子(明治大学情報コミュニケーション学部准教授・塾員)
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
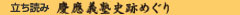 |
|
慶應義塾も今日では大学の学部は十に増え、主なキャンパスも六を数える。どの世代も、どの学部の出身でも、共に思い出の一齣を持つ場所をそのキャンパスに探すことは出来なくなった。・・・
|
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <話題の人> |
| 一〇一歳の現役サラリーマン |
| |
|
 |
福井福太郎さん
(東京宝商会顧問・塾員) |
| |
インタビュアー
村田作彌(慶應義塾高等学校同窓会顧問・事務局長) |
| |
|
| 何歳になっても働き続けること――高齢社会となった現在の日本において一つの理想の姿なのでしょう。福井さんは昭和11年に塾をご卒業。長い軍隊経験を経て、様々な職に就かれ、101歳となる現在も現役サラリーマンとして辻堂から神田まで通勤されています。関東大震災、二・二六事件、太平洋戦争、戦後の混乱期と続いた大変な激動の時代を淡々と穏やかに生きてこられた福井さんの姿に、真の強さを感じました。
|
| |
|
 |
| <三人閑談> |
| 富士山と日本人 |
宮家 準(慶應義塾大学名誉教授)
明石欽司(慶應義塾大学法学部教授)
中島直人(慶應義塾大学環境情報学部准教授)
|
|
| 今年6月、世界文化遺産に登録された富士山。今夏もたくさんの登山客でにぎわいましたが、その歴史や文化はあまりよく知られていないのではないでしょうか。麓の富士吉田市は慶應義塾と包括協定を結んでおり、このほど「慶應の水」も発売されるなど以前から大変関係の深い場所です。日本人はなぜ富士山に魅せられるのか、日本人にとって富士山とはどんな存在なのか。ゆかりのある三人がじっくり語りました。 |
| |
| <連載> |
| KEIO MONO MUSEUM53 |
|
| 第一回普選 選挙ポスター |
解説 玉井 清 |
|
大久保忠宗 |
|
山内慶太 |
|
| |
| <演説館> |
| アマゾンの違法伐採を防止する日本の技術 |
小野誠 |
|
| <その他> |
丘の上 |
遠藤まゆみ、小山久美、川合伸太郎、佐々木信也 |
塾員クロスロード |
浅井亮博 |
| Researcher's Eye |
大矢玲子、庄司克宏、野村浩二 |
| 執筆ノート |
『バチカン近現代史──ローマ教皇たちと「近代」との格闘』
松本佐保
『若者問題の社会学──視線と射程』
井本由紀(共編著・監訳)
『日系人を救った政治家ラルフ・カー──信念のコロラド州知事』
池田年穂(訳)
|
社中交歓(銭湯)
|
松田橿雄、中川良隆、酒井正文、権丈善一 |
新学部長・
研究科委員長の横顔
|
商学部長・商学研究科委員長 金子 隆君 樋口美雄
総合政策学部長 河添 健君 阿川尚之
薬学部長・薬学研究科委員長 望月眞弓君 中島恵美
|
|
|
|
|
|