慶應義塾機関誌
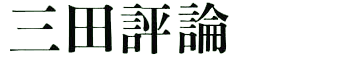
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
| 〈座談会〉メディアの変化のなかで大学図書館はどこへ向かうか |
吉見俊哉(東京大学副学長、同大学院情報学環教授)
安達 淳(国立情報学研究所副所長、同コンテンツ科学研究系教授、同学術基盤推進部長)
竹内比呂也
(千葉大学附属図書館長、同文学部教授、アカデミック・リンク・センター・塾員)
羽田 功(慶應義塾日吉図書館長(大学日吉メディアセンター所長)、経済学部教授)
田村俊作(慶應義塾図書館長(大学メディアセンター所長)、文学部教授) |
|
| |
本年、慶應義塾図書館が開館から100年を迎え、4月には記念式典が三田キャンパスで行われました。近年とくにデジタルメディアの発達により、従来の蔵書というイメージから大きな変化を遂げている図書館。100年以上“大学の心臓”として教育・研究活動の中心として担ってきたその役割を振り返り、これからの展望を考えていく特集です。 |
| |
| 〈関連記事〉 |
大学図書館の役割と将来
倉田敬子(慶應義塾大学文学部教授)
百年を書物抱きて
澁川雅俊(慶應義塾大学元メディアネット事務長、元環境情報学部教授)
慶應義塾図書館開館一〇〇年を迎えて
石黒敦子(慶應義塾大学三田メディアセンター事務長)
|
| |
|
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
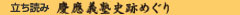 |
|
松永安左エ門は、明治八年十二月一日、長崎県壱岐の印通寺で造り酒屋や回船問屋を営む商家の長男(幼名・亀之助)として生まれる。『学問のすゝめ』に感激し、明治二十二年上京、慶應義塾に入学。明治二十六年父の死により帰郷し、家督を相続し三代目安左エ門を襲名。明治二十八年、家業を弟・英太郎にゆだね、義塾に復学した・・・
|
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆平成二十四年度大学入学式 |
|
| 清家 篤(慶應義塾長) |
| |
|
滝鼻卓雄(株式会社読売巨人軍取締役最高顧問、慶應義塾評議員)
大橋光夫(昭和電工株式会社相談役、慶應義塾評議員) |
| |
| |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <三人閑談> |
| 名刺の威力 |
森永卓郎(経済アナリスト、獨協大学経済学部教授)
高木芳紀(名刺アドバイザー、日本名刺協会理事)
市瀬豊和(株式会社山櫻代表取締役社長・塾員)
|
|
| ビジネスの場面で欠かせない名刺。小さなツールですが相手に与える印象は大きく、名刺交換をきっかけに人脈やビジネスチャンスが広がることもあります。この名刺、そもそもどんなものなのか。そして優れた名刺、相手に訴える名刺のポイントとは。いずれも独特のこだわりを持つコレクター、アドバイザー、そして老舗メーカー社長の3人による楽しいお話です。 |
| |
| <連載> |
| KEIO MONO MUSEUM39 |
|
| 駒井哲郎画「三田評論」掲載カット |
解説 渡部葉子 |
|
大久保忠宗 |
|
加藤三明 |
| |
|
| <その他> |
丘の上 |
加瀬邦彦、河合正朝、紀田順一郎、山崎 洋 |
演説館 |
磯田道史 |
塾員クロスロード |
佐々木 彰 |
| Researcher's Eye |
川俣雅弘、水島 徹、神吉創二 |
| 書評 |
『銀座復興』(水上瀧太郎著)
小泉 妙
『長州の経済構造一八四〇年代の見取り図』(西川俊作著)
速水 融
|
| 執筆ノート |
『北村美術館 四季の茶道具――茶友への誘い』
木下 收
『アートを生きる』
南條史生
『習近平――共産中国最弱の帝王』
矢板明夫 |
| 社中交歓(長靴) |
東條英樹、水野 尚、西井英正、矢澤健太郎 |
| 追想 |
村上元彦先生を偲んで/河村 悟
鐵野善資先生を送る/三瓶愼一 |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|