慶應義塾機関誌
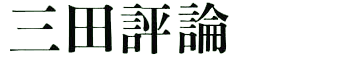
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
| 〈座談会〉問い直されるコーポレート・ガバナンス |
亀川雅人(立教大学大学院ビジネスデザイン研究科(経営学部)教授)
八田進二(青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科長・教授・塾員)
矢島 格(前農林中金総合研究所調査第二部長、上武大学ビジネス情報学部教授・塾員)
菅原貴与志
(慶應義塾大学大学院法務研究科教授、弁護士・塾員)
菊澤研宗(慶應義塾大学商学部教授) |
|
| |
コーポレート・ガバナンスという言葉が日本に定着して約20年になります。昨年相次いで日本の大企業で起こった不祥事をきかっけに、日本企業のガバナンスをあらためて問い直す動きが高まるなか、企業のガバナンスを支える社会のあり方、歴史や文化を踏まえた日本ならではの特徴まで踏み込み、グローバル時代を生きる日本企業にとって最適なガバナンスを考えていく特集です。
|
| |
| 〈関連記事〉 |
コーポレート・ガバナンスと企業業績
岡本大輔(慶應義塾大学商学部教授)
ステークホルダー論から見たコーポレート・ガバナンスの動向
出見世信之(明治大学商学部教授)
|
| |
|
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
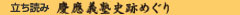 |
|
藤山雷太
藤山雷太(らいた)は、文久三年八月一日(一八六三年九月十三日)、肥前国松浦郡二里村大里(現佐賀県伊万里市)の庄屋を務めていた、佐賀藩士藤山覚右衛門の四男として生まれた。雷太誕生の日が大里の神之原(かみのはら)八幡宮の祭日で村芝居が掛かっており、源氏再興の児が生まれるという筋であった・・・
|
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆平成二十三年度大学卒業式 |
|
| 清家 篤(慶應義塾長) |
| |
|
| 比企能樹(慶應義塾大学医学部三四会会長・慶應義塾理事) |
| |
| |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <話題の人> |
| 「140文字が生み出す新たな社会基盤」 |
| |
|
 |
近藤正晃ジェームスさん
(ツイッター日本代表・塾員) |
| |
インタビュアー
村井 純(慶應義塾大学環境情報学部長) |
| |
|
| 世界を代表するソーシャルメディアのひとつとして定着したTwitter。とくに日本での普及のスピードはすさまじく、日本語でのツイート数は英語に次ぐ第2位、また1秒当たりのツイート数の記録は日本が保持しています。なぜツイッターは日本でこれほどまで受け入れられたのか、そして人々が日々発信している「140文字」から見た現在の社会とは。爆発的な広がりを見せるツイッターの日本代表を務める近藤さんへのインタビューです。 |
| |
|
| |
|
| <三人閑談> |
| コケティッシュな苔たち |
有川智己(鳥取県立博物館主任学芸員)
藤井久子(編集ライター、苔愛好家)
村田行雄(盆栽師・塾員)
|
|
| ギンゴケ、ヒカリゴケ、ゼニゴケ…、四億年前から存在し、大都会から極地まであらゆるところに生息している小さな苔たち。実は日本には1700種もの苔があることをあなたは知っていますか? 今回はそんな苔たちに魅了された苔男(コケメン)・苔女(コケガール)が集合し、古今東西の苔話に花を咲かせます。ユルくてコケティッシュな苔の世界をご堪能ください。 |
| |
| <連載> |
| KEIO MONO MUSEUM38 |
|
| 堀内敬三自筆「若き血」楽譜 |
解説 都倉武之 |
|
大久保忠宗 |
|
大澤輝嘉 |
| |
|
| <その他> |
丘の上 |
西村和子、英 正道、宮城盛孝、湯浅譲二 |
演説館 |
鈴木康友 |
塾員クロスロード |
宮島将郎、西村 琢 |
| Researcher's Eye |
神部信幸、筧 康明 |
| 執筆ノート |
『人はなぜ騙すのか――狡智の文化史』
山本幸司
『娯楽と癒しからみた古代ローマ繁栄史
――パンとサーカスの時代』中川良隆
『すぐれたゴルフの意思決定――「熟慮速断」の上達法』
印南一路 |
| 社中交歓(兜) |
片岡秀之、和田祐之介(光弘)、羽田紀康、清水研助 |
| 追想 |
内池慶四郎先生を悼む/池田真朗 |
| 時は過ぎゆく |
小泉淳作君を想う/川崎悟郎 |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|