慶應義塾機関誌
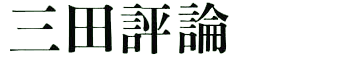
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
2011年も暮れようとしています。本年日本にとって最大の出来事である東日本大震災とそれに伴う原発事故は、「こころ」や考え方の面でもはかり知れない影響を日本人に与えていると思います。大災害により亡くなった方をどうやって弔うのか、震災で見えてきた日本人の心性の特徴とは何か、また震災後、日本人の行動やこころの変化はどのようなものか。座談会と特集記事で考えていきます。 |
| |
|
|
| [座談会] 大災害に見る家族、地域、人とのつながり |
鈴木岩弓(東北大学大学院文学研究科教授)
戸松義晴(全日本仏教会事務総長、日本宗教連盟事務局長・塾員)
原 礼子(慶應義塾大学看護医療学部教授)
渡辺秀樹(慶應義塾大学文学部教授、大学院社会学研究科委員長)
|
| [関連記事] |
震災後、くらしと価値観はどう変わったか
福士千恵子(読売新聞東京本社生活情報部長)
|
「被災地」に行くのではなく、「南三陸町」へ行く
長沖暁子(慶應義塾大学経済学部准教授)
|
| |
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
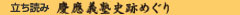 |
|
今年も六月十日に、信濃町キャンパスの北里記念医学図書館の二階にある北里講堂において北里記念式が開催された。毎年、初代医学部長北里柴三郎の命日の前後に挙行される式で、塾長、医学部長、三四会(医学部同窓会)長、北里家代表の挨拶等からなる記念式に引き続き、北里賞と北島賞の授賞式、更に受賞者による講演が行われた・・・…
|
|
|
| |
| 次号予告 |
| 2012年1月号 No.1152 |
◆特集◆
新春塾長対談 |
|
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <話題の人> |
「ラジオを元気にするために」
岩下 宏さん(radiko社長・塾員) |
インタビュアー
近藤 進(株式会社電通ラジオ局 業務統括部・塾員)
|
|
| |
| 地上波のラジオを、インターネットでも同時に配信する――この新しい試みを手掛ける岩下宏さん。東日本大震災時に改めてその存在感が見直されたラジオを、一人でも多くの人に聞いてもらうためにはどうすればよいか。塾生時代の「放送研究会」の思い出にも触れつつ、ラジオ「復権」への思いを語っていただきました。 |
 |
| <三人閑談> |
| ハードボイルドのアメリカ |
小鷹信光(ハードボイルド研究家・翻訳家)
松坂 健(西武文理大学サービス経営学部教授・塾員)
生井英考(立教大学社会学部教授・塾員)
|
|
| |
| かつて、キザでいなせで、ちょっと人情があって、そして孤独な名探偵たちがいました。ダシール・ハメットやレイモンド・チャンドラーが描いた彼らは、どのように生まれたのか。2010年代のいま、「ハードボイルド」はもはや過去のものなのか。ハメット没後50年を迎えた今年、改めてハードボイルドの魅力、そしてそれを生み出した「アメリカ」の姿についてホットに、クールに語り尽くします。 |
 |
| <連載> |
| KEIO MONO MUSEUM33 |
|
| 福澤諭吉筆「贈医」書幅 |
解説 山内慶太 |
|
大久保忠宗 |
|
山内慶太 |
| |
|
| <その他> |
丘の上 |
佐々木正五、高山正也、山本道子 |
演説館 |
松岡由幸 |
塾員クロスロード |
岩田真一、熊谷知子 |
| Researcher's Eye |
穂刈 享、山川隆一 |
| 執筆ノート |
『銀座の画廊巡り――美術教育と街づくり』野呂洋子
『リスクの誘惑』坂上貴之(共編)
『福沢諭吉――「官」との闘い』小川原正道 |
| 社中交歓(笛) |
来代正紀、須田芳正、堀田峰明、柴本 幸 |
| <第三十六回小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト結果発表> |
| <追想 西岡秀雄君――新しい思考を求め続けた大先輩> |
井口悦男 |
|
|
| <KEIO Report> |
ラビンドラナート・タゴール生誕150年記念シンポジウム
「慶應義塾とタゴール」の開催
|
臼田雅之 |
G‐SECアメリカ研究プロジェクト始動
――第一回シンポジウム報告 |
大串尚代 |
|
| <「三田評論」年間総目次〈平成23年1月〜12月〉> |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|