慶應義塾機関誌
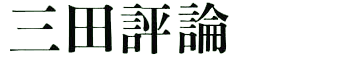
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
| ◆特集 |
|
| |
学生の留学離れが、報道などで伝えられています。海外留学は世界の多様性を発見し、また、自分の可能性に気付くチャンスであることは間違いありません。若いうちだからこそできる「かけがえのない体験」を過去の留学生たちはどのように過ごしてきたのか。いまの学生の留学への志向を勇気づける特集です。 |
| |
|
|
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| [座談会] 多様性に触れ、自分の可能性を広げる留学体験 |
| |
スザーヌ・バサラ(駐日米国大使上級顧問)
岡野光喜 (スルガ銀行代表取締役社長兼CEO・塾員)
沼田勇太郎 (北京電通広告有限公司勤務・塾員)
阿川尚之 (慶應義塾常任理事、総合政策学部教授)
|
| [関連記事] |
慶應義塾における海外大学との学生交流――国際センターの取り組み
友岡 賛
(慶應義塾大学国際センター所長、
同日本語・日本文化教育センター所長、同商学部教授)
|
| |
私の「漂流」体験
堀 茂樹 (慶應義塾大学総合政策学部教授)
|
| |
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
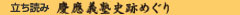 |
|
なぜ日吉に海軍が?
話は太平洋戦争の後期、坂道を転がり落ちるように戦局が悪化していく頃である。昭和十八(一九四三)年十二月、在学中の学生は徴兵されないというそれまでの徴兵猶予が、文系学生について停止され、在学中であっても二十歳に達していれば徴兵されるいわゆる「学徒出陣」によって多くの学生が在籍のまま入隊していった。キャンパスに残されたのは二十歳(その後十九歳に引き下げ)に満たないか、病気などの理由により兵役に不適と判定された学生など少数で、校舎のほとんどは空教室となっていた……
|
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆講演録 |
日本の経済針路
鈴木淑夫 (元日本銀行理事、元野村総研理事長、元衆議院議員、経済学博士) |
|
| ◆その他の企画 |
| <三人閑談> |
| 朝市に行こう! |
中川誼美((株)吉水代表取締役・塾員)
神田より子(敬和学園大学人文学部教授・塾員)
松田慶子(毎日アースデイ(株)取締役。アースデイマーケット実行委員・塾員) |
|
| 今回は、それぞれコンセプトの異なる朝市を開催している3人の女性が登場です。築地本願寺で昔ながらの朝市を主宰する旅館女将の中川さん、代々木公園でファーマーズマーケットを開く松田さん、そして江戸時代から続いてきた伝統的な朝市を新潟・新発田で復活させた神田さん。私たちの「暮らし」を変えるきっかけにもなりうる朝市の魅力と未来をたっぷり語っていただきました。 |
 |
| <巻頭随筆 丘の上> |
桑田 收、駒井美子、佐藤玲子、深草アキ |
| |
|
| <連載> |
KEIO MONO MUSEUM26
幼稚舎・児童図書室閲覧机(解説 白井文子)
|
|
大久保忠宗 |
|
都倉武之 |
| |
|
| <その他> |
演説館 |
樫尾直樹 |
塾員クロスロード |
葉山耕司 |
| Researcher's Eye |
築山和也、丸田千花子、副島研造 |
| 執筆ノート |
『日本林業はよみがえる――森林再生のビジネスモデルを描く』
梶山恵司
『蒋介石と日本――友と敵のはざまで』
黄 自進
『東京今昔歩く地図帖――彩色絵はがき、古写真、古地図でくらべる』
井口悦男(共著) |
| 社中交歓(城) |
秋岡 毅、井口亮太、吉田 真、眞田幸俊 |
| <追想> |
| 槇田先生を偲んで |
伊藤隆一 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|