慶應義塾機関誌
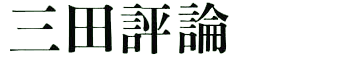
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
日米安保が現行のものに改定されてちょうど50年である本年は、奇しくも日米関係、そして東アジア情勢とも多難な年になっています。普天間問題で噴出した日米同盟の揺らぎ、最近の尖閣諸島問題を考える上で日米安保の重要性の理解はカギとなるものと言えそうです。 |
| |
| ◆座談会 |
| 東アジアのなかの「日米安保」 |
|
我部政明 |
|
琉球大学法文学部教授、琉球大学国際沖縄研究所所長 |
久保文明
|
|
東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
添谷芳秀 |
|
慶應義塾大学法学部教授、慶應義塾大学東アジア研究所所長 |
赤木完爾 |
|
慶應義塾大学法学部教授 |
| ◆関連記事 |
仏作って魂入らぬ日米安保50年
|
伊奈久喜(日本経済新聞特別編集委員) |
ワシントンからみた日米関係――日米同盟はなぜ揺らいだか
|
古森義久(産経新聞ワシントン駐在編集・特別委員兼論説委員・塾員) |
地政学からみた日米同盟
|
秋元千明(NHK解説委員) |
|
|
|
| |
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
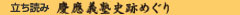 |
|
出生から普通部編入まで
久保田万太郎は、明治22(1889)年、浅草田原町の袋物製造販売を業とする父勘五郎、母ふさの次男(長男は夭逝)として生まれた。馬道の尋常高等小学校から府立三中(現両国高校)に進むが、文学に没頭し、4年に進級の際代数の成績が悪く落第してしまい、慶應義塾普通部の3年へ編入することになった・・・
|
|
|
|
|
 |
|
|
| <福澤諭吉先生生誕175年 記念式典・講演会> |
| |
福澤諭吉先生生誕175年記念式典・講演会について |
慶應義塾総務部 |
挨拶 |
清家 篤 |
| |
|
| ◆その他の企画 |
| <三人閑談> |
| 早慶応援物語 |
| 三木佑二郎(ビジネス総合研究所代表取締役) |
| 三田 完(作家・塾員) |
田中 知之(慶應義塾大学信濃町メディアセンター職員) |
|
| 秋の六大学リーグ戦たけなわの季節、今月末の早慶戦を楽しみにしていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。国民的行事とも言われ、日本のスポーツ史にかくたるページを刻んできた早慶戦は、方や学生による数々の応援文化を生み出してきた場でもあります。コンバットマーチに負けずにダッシュケイオウを皆で歌いに神宮へ行こう! |
 |
| <巻頭随筆 丘の上> |
田辺征夫、中村政行、山口 寛、横山 潤 |
| |
|
| <講演録> |
歴史人口学――出逢い、史料、観察結果、課題 |
速水 融 |
| |
|
| <連載> |
KEIO MONO MUSEUM20
農高時代の農具と焼き鏝(ごて) (解説 宮橋裕司)
|
|
大澤輝嘉 |
|
大久保忠宗 |
| |
|
| <その他> |
塾員クロスロード |
岡田淳一、田代治之 |
| Researcher's Eye |
酒井良清、阪埜浩司、松浦寿幸 |
| 執筆ノート |
『東京ふつうの喫茶店』
(泉 麻人)
『古書の森 逍遙――明治・大正・昭和の愛しき雑書たち』
(黒岩比佐子)
『近代日本の戦争と宗教』
(小川原正道) |
| 社中交歓(きのこ) |
石井達朗、
湯木俊治、
三品浩一、
犀川陽子 |
| <追想> |
| 庭田範秋先生を偲ぶ |
堀田一吉 |
| 石井裕正名誉教授の思い出 |
朝倉 均 |
| <「三田文学創刊一〇〇年展」の開催> |
坂上 弘
|
| <大学附属研究所斯道文庫開設50周年を迎えて> |
高橋 智
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|