�@�@�c��`�m�@�֎�
�@![�O�c�]�_](img/def/title.gif)
�@�@����31�N3���n���i����1��1�����s�j
�@�@ ���s�F�c��`�m�@�ҏW�l�F�c��`�m�L���@�ҏW�E����F�c��`�m��w�o�ʼn�
|
|
 |
2018�N6�����\�� |
|
       ![�O�c�]�_�Ƃ�](img/def/menu/off_images/menu_bar_08.gif)          |
| |
|
|
| �����P��P�����s |
| �ō����i�F451�~�i�{�� 410�~�j |
| ����w�ǁF4,700�~�i�ŁE�������j |
| �ɂ��� |
 |
 |
|
 |
|
| |
| �����W |
|
�r�b�O�f�[�^�A�I�[�v���f�[�^�̎���ɂȂ�A�u���v�v�ɑ���C���[�W���傫���ς�낤�Ƃ��Ă��܂��B�c��Ɏ擾�ł���悤�ɂȂ����f�[�^���ǂ̂悤�Ɏ戵���A���͂��Ė������Ɍ��т���̂��B���A�������ŁA���́u�f�[�^�T�C�G���X�v�̗͂����߂��A�w�Z�����Љ�̂Ȃ��ŁA�����ɐg�ɕt���Ă��������傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă��Ă��܂��B�V�������v�̗͂Ƃ͉����B���w�Ƃ��Ă̓��v�w�̕K�v�������炽�߂čl������W�ł��B
|
| |
| |
| �q���k��r�f�[�^�T�C�G���X����̓��v���� |
| |
�{�]��F�i�����ȓ��v���C����������b���[���v���헪���i���j
�ێR�D��i�m�g�j����ljȊw�E���ԑg�f�B���N�^�[�j
�ց@�L�v�i���E�V�X�e�������@�\ ���v�����������������E���I�m���j
����@���i�c��`�m��w�����w�����A���w�������j
�n�Ӕ��q�q�i�c��`�m��w��w�@���N�}�l�W�����g�����ȋ����i�i��j�j
|
|
| |
| �q�֘A�L���r |
| |
�V���Ɠ��v���e���V�[���������̓`�����Ǝ���
���c���j�i�ǔ��V�������{�А��_�������j
|
| |
�č����w�Z�̖������^�̓��v�Ȋw�I�v�l�͈琬
��@����q�i�c��`�m��w���H�w�������Ȋw�ȋ����j
|
| |
���V�@�g�Ɠ��v�w�������w�̕��@
�n�ꍑ���i�c��`�m�Ó쓡�E���������@�A���V�����Z���^�[�����j
|
| |
|
|
|
|
| �@�c��`�m�ێ��� |
��Z���v���m���ƓĎu�Ƃ̊F�l�ɂ��A�`�m�̋��猤�������������x������ړI�Őݗ����ꂽ�ꐢ�I�]�̗��j��L����g�D�ł��B
����̊F�l�ɂ͂��������ԁw�O�c�]�_�x�悢�����܂��B |
|
|
| |
|
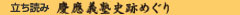 |
|
��M�z�����v�C���^�[�`�F���W����⑺�c�Ɍ������A�����l�\�l�����𑖂邱�Ə\�ܕ��ō��v�s�u��̏W���Ɏ���B�u��ɂ́u�_�Áv���𖼏��Ƃ��������A�����k�Ƃ̌���œ�k������Ɉɓ��_�Ó���肱�̒n�ɈڏZ�����Ɠ`������B�c
|
|
|
|
|
 |
|
|
| �����̑��̊�� |
| ���b��̐l�� |
| �`�[���͂Ŏ��g�ށu�����Ɨǂ��N���}�Â���v |
| |
|
 |
��ؕq�v����
�i�g���^������ ���i���{�� �卸�E�m���j |
| |
�C���^�r���A�[
��R������i���m�g�j�L���X�^�[�A���P�C�c�[���E�m���j |
| |
|
| �b��̃R���p�N�g�J�[�u�p�b�\�v�̊J���ӔC�҂ł�������́A����܂ł��u�����Ɍ������N���}�Â���v����|���Ă��܂����B�Z�p�╔�i�����ł͂Ȃ��A�l���܂Ƃ߂�����ł�����卸���`�[�t�G���W�j�A�Ƃ����d���B���̍���ɂ́A�m�Ŕ|�����u�`�[���́v������܂����B
|
| |
|
 |
| ���O�l�Ւk�� |
| �Õ��T�K�̂��T�� |
���V�����Y�i��j�W���[�i���X�g�E�m���j
���������i���َq���l�Êw�ҁE�m���j
����@���i�c��`�m��w���_�����j |
|
| �ߔN�A�Ⴂ�����𒆐S�Ɂu�Õ��v�ւ̊S�����܂��Ă��܂��B���̓Ɠ��̔������p�`�͂������A�Ñ�ɂ��̂悤�ȋ���Ȍ��������ǂ̂悤�ɑ������̂��A�Ȃ��S���ɓ����`�̂��̂���������̂��ȂǁA�Õ����߂��邳�܂��܂ȓ�����������������Ă�݂܂���B�Ñ�ւ̃��}�����������Ă���Ւk�ł��B
|
| |
| ���A�ځ� |
| �@KEIO MONO MUSEUM65 |
|
| �@������i�E������ |
����@���쌴���� |
�@����ɐ����镟�V�@�g�̂��Ƃ@����95
|
��v�ے��@ |
|
�����O�� |
|
| �@ |
| �������ف� |
| �@�x���a���̎Љ�I���p�����u�Љ�I�����s��v�`���Ɍ����� |
�L���뗲 |
|
|
|
| �����̑��� |
�u���w�i�T�C�G���X�j�v�ɂ���Ēn���Љ�̎����\�������߂�
���Ɓ@�āi�c��`�m���j |
|
�@���f�B�A�̌������Ɖz���������q�h�o�d��Z��l�������� |
�R�{�M�l�i�c��`�m��w�@�w�������A���f�B�A�E�R�~���j�P�[�V�������������j |
�@�u�̏� |
�����ʓ�A���ۈɓs�q�A�����@���A���{���Y |
�@�m���N���X���[�h |
���g�E�P�A�ߖؗR���q |
| �@Researcher's Eye |
���`�����A�����@�ցA�{�c����
|
|
|
|
| �@���M�m�[�g |
�w���������Ε����ɂ����鄟������������������̋^��x
�����@�T�i��j
�w�����F���ƂƔe���Ȃ����E�x
�A���z�q
|
|
|
|
| �@������
�i� �j |
�X��I�T���A�y�c�����A����c���A�R�{�p�j
|
|
|
|
|
|