慶應義塾機関誌
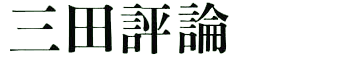
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
| 〈座談会〉「健康寿命」を延ばすために何が必要か
|
安川拓次(花王株式会社執行役員ヒューマンヘルスケア事業部ユニットフード&ビバレッジ事業グループ長)
宮地元彦(独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研究部長)
福吉 潤(株式会社キャンサースキャン代表取締役社長・塾員)
伊藤 裕(慶應義塾大学医学部内科学教室腎臓内分泌代謝内科教授)
武林 亨(慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授)
|
|
| |
高齢社会を迎え、クオリティ・オブ・ライフの高い一生を送るため、健康への関心はますます高くなっています。メタボリックシンドロームという言葉がさかんに言われ、予防医療の重要性が高まるなか、「健康寿命」をいかに伸ばすかが課題です。医療のみならず、健康食品、運動、ヘルスコミュニケーションの分野の第一人者が集まった座談会からは様々な取り組みの具体例が示されます。
|
| |
| 〈関連記事〉 |
健康日本21(第二次)の推進
宮嵜雅則(厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長・塾員)
無病を目指して
── 慶應義塾大学病院予防医療センターの開設にあたって
杉野吉則(慶應義塾大学病院予防医療センター長)
|
| |
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
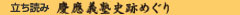 |
|
慶應義塾は私立である。有志が出し合わない限り、お金はどこからも湧いて出ない。しかも国から正式な「大学」の資格を与えられているのは帝国大学(東京・京都・東北・九州)のみで、私立である慶應は、法律上「専門学校」として扱われていた。そういう官尊民卑甚だしい時代に建ったのが、今日でも義塾のシンボルとされる赤?瓦の慶應義塾図書館(旧館)であった。・・・
|
|
|
| |
| 次号予告 |
| 2013年1月号 No.1163 |
◆特集◆
新春塾長対談 |
|
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <話題の人> |
| 「世界に発信する音楽ホールを」 |
| |
|
 |
福本ともみさん
(サントリーホール総支配人・塾員) |
| |
インタビュアー
平野 昭(慶應義塾大学文学部美学美術史学専攻教授) |
| |
|
| 国内外の数々の著名音楽家を招いてきたサントリーホール。その総支配人に、今年女性として初めて福本さんは就任しました。総支配人の仕事とは何か、そして作り手や聴き手にとって心地よい音楽ホールとはどんなものか。「常に新しいものを」日本の音楽界に提供し続けるサントリーホールを手掛ける福本さんから、真摯な「プロフェッショナル」の言葉を聞くことができました。 |
| |
|

|
| <三人閑談> |
| タテ書き? ヨコ書き? |
矢口博之(東京電機大学理工学部准教授)
アンドルー・アーマー(慶應義塾大学文学部教授)
屋名池 誠(慶應義塾大学文学部教授)
|
|
|
タテにもヨコにも、文字通り「縦横無尽」に書くことができる言語=日本語。ふだん日本語を使っている私たちにとってこれは当たり前のことですが、世界的には極めて珍しい特徴と言えます。日本語の「ヨコ書き」はそもそもいつ、どのように始まったのか。そしてタテ書き、ヨコ書きの未来は。いわゆる「書字方向」をめぐるおしゃべりは、改めて日本語の奥深さ、面白さに気づかせてくれます。 |
| |
| <連載> |
| KEIO MONO MUSEUM44 |
|
| 福澤諭吉の散歩グッズ |
解説 都倉武之 |
|
大久保忠宗 |
|
都倉武之 |
| |
| <演説館> |
「世界」に想いを馳せるリーダーを
──「ビヨンドトゥモロー」の活動 |
坪内 南 |
| |
|
| <その他> |
丘の上 |
桑原敏武、堂園凉子、聖田京子、藤井清孝 |
塾員クロスロード |
那須規子、北川修一 |
| Researcher's Eye |
藤木健二、岡 檀 |
| 執筆ノート |
『泉鏡花 ── 百合と宝珠の文学史』
持田叙子
『ヒトはなぜ難産なのか ── お産からみる人類進化』
奈良貴史
『貴重書の挿絵とパラテクスト』
松田隆美(編)
|
| 社中交歓(ベル) |
鈴木邦彦、椎野通孝、田代 肇、夏野 剛 |
|
| <第三十七回 小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト結果発表> |
|
| <『三田評論』年間総目次〈平成二十四年一月〜十二月〉> |
|
|
|
| |
| |
|
|
|