慶應義塾機関誌
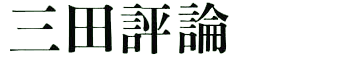
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
| 〈座談会〉技術を支える倫理観を育てるために |
大輪武司(金沢工業大学客員教授、元東芝首席技監)
高嶋哲夫(小説家、東京工業大学非常勤講師)
大場恭子(金沢工業大学科学技術応用倫理研究所研究員)
梅津光弘(慶應義塾大学商学部准教授)
前野隆司(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科委員長) |
|
| |
「3・11」から一年――日本を襲った震災、とりわけ原発事故災害は、われわれの社会に様々な問いを投げかけています。巨大エネルギーシステムを動かしてきた技術にはどのような倫理的な視点/議論が欠けていたのか。原発についての国民的な議論が必要とされるなか、技術者だけではなく国民一人ひとりのなかに、技術を使うための倫理観を育てる必要性を問う特集です。
|
| |
| 〈関連記事〉 |
「技術者倫理教育における哲学の役割」
瀬口昌久(名古屋工業大学大学院工学研究科教授) |
| |
|
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
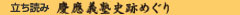 |
|
福澤先生は、蘭学修業のため安政元(一八五四)年二月、数え十九歳の時から長崎に留学していた。先生は、やはり長崎に蘭学の勉強に来ていた中津藩家老の息子奥平壱岐の世話になっていたが、先生の蘭学の上達があまりにも早いため、壱岐の妬みを受け、壱岐の奸計によって先生は中津に帰ることになってしまった・・・
|
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆巻頭随筆 丘の上――震災から一年 |
| |
「大震災と慶應義塾の貢献」(佐藤久一郎)
「原発対処に誓った独立自尊」(長島昭久)
「社中の年中行事」(服部禮次郎)
「聞き書き」(吉増剛造) |
|
| |
| |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <話題の人> |
| パリ・コレ進出30年の軌跡 |
| |
|
 |
山本耀司さん
(ファッションデザイナー・塾員) |
| |
インタビュアー
熊倉敬聡(慶應義塾大学理工学部教授) |
| |
|
| 世界に衝撃を与えたパリ・コレクションでのデビューから30年を迎え、昨年フランス芸術文化勲章の最高位コマンドールを受章されたデザイナー・山本耀司さん。今なお最前線で活躍する巨匠を突き動かしているものは何なのか。これまでの「反逆」のキャリアを振り返るとともに、これからをどう生きるか、震災後の日本への思いなど、率直な言葉で語って下さいました。 |
| |
|
| |
|
| <三人閑談> |
| 躍動する理系女子(リケジョ)たち |
井上裕美(日本アイ・ビー・エム(株)・塾員)
岩崎由香(慶應義塾大学医学部分子生物学教室特任助教・塾員)
松尾亜紀子(慶應義塾大学理工学部教授)
|
|
| 最近、企業や研究機関でも理工系出身の女性=「理系女子(リケジョ)」への注目が高まり、大学も女子学生向けの獲得に躍起です。実際、理系女子たちはどのような日常を過ごしているのでしょうか。クラスの男子との関係は? 卒業後のキャリアは? ――なかなか聞けない「本音トーク」を、慶應義塾の誇る理系女子3人が繰り広げます。 |
| |
| <連載> |
| KEIO MONO MUSEUM36 |
|
| 大ホールの銘板 |
解説 都倉武之 |
|
大久保忠宗 |
|
加藤三明 |
| |
|
| <その他> |
丘の上 |
佐藤久一郎、長島昭久、服部禮次郎、吉増剛造 |
演説館 |
石橋 徹 |
塾員クロスロード |
田村明弘、齋藤貴臣 |
| Researcher's Eye |
溝口哲郎、神崎 晶、飯盛義徳 |
| 執筆ノート |
『江戸の縁起物――浅草仲見世 助六物語』
木村吉隆
『福澤諭吉と女性』
西澤直子
『皇軍兵士とインドネシア独立戦争――ある残留日本人の生涯』
林 英一 |
| 社中交歓(マスク) |
吉村昭彦、堀内康雄、牛島利明、原田曜平 |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|