慶應義塾機関誌
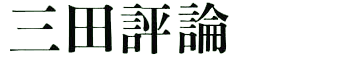
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
東日本大震災から3カ月が経とうとしています。復興へ向かう時期に当たり、私たち一人ひとりが社会のありようを見つめ直すなか、福澤諭吉の『時事新報』での濃尾地震、三陸大津波時の義援金呼びかけなど「民の力」を生かした震災への対応は大いに学ぶべきものがあります。現在の状況を踏まえ、「民」の役割を歴史的に考える座談会、さらに濃尾地震時の『時事新報』全関連社説等を掲載・解説する記事で、これからの日本の復興への道のりを考えていきます。また巻頭の随筆では塾名誉教授四人に震災への思いを綴ってもらいました。 |
| |
|
|
| [座談会] 「民の力」を復興に生かすために歴史に学ぶこと |
| |
井上 潤(渋沢史料館館長)
橋本五郎(読売新聞特別編集委員・塾員)
加藤三明(慶應義塾幼稚舎長)
都倉武之(慶應義塾福澤研究センター専任講師)
山内慶太(慶應義塾大学看護医療学部教授)
|
| [関連記事] |
『時事新報』と濃尾地震、三陸大津波
編・都倉武之(慶應義塾福澤研究センター専任講師)
|
|
| |
|
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
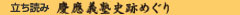 |
|
浜木綿(はまゆう)は、ヒガンバナ科の多年草で、花の様子が木綿(ゆふ)を垂らしたようであることが名の由来である。木綿はコウゾなどの樹皮を細く裂いて作った繊維から作った布で、古代から神事などに用いられてきたものである。花は八月に見ごろを迎える。水はけが良く日あたりの良い場所を好み、主に温暖な海浜で見られる。道ばたや公園、庭に植えられることもあり、宮崎県の県花となっている……
|
|
|
|
|
 |
|
|
| <巻頭随筆 丘の上――震災に思う> |
| 大震災から学ぶもの |
鈴木孝夫 |
| 縄文式復興計画 |
近森 正 |
| 宝永地震、昭和南海地震と東日本大震災 |
速水 融 |
あるイギリスの学会で学んだこと |
森岡敬一郎 |
| |
|
| ◆慶應義塾による蹤東北地方太平洋沖地震義援金蹙へのご協力のお願い |
|
| ◆その他の企画 |
| <三人閑談> |
| オペラに行こう! |
加藤浩子(音楽物書き・塾員)
朝岡聡(フリーアナウンサー、コンサートソムリエ・塾員)
河村俊隆(慶應義塾高等学校教諭)
|
|
| |
| オペラにハマってしまった3人による楽しいオペラ閑談です。オペラの魅力は何と言っても歌手の「声」の素晴らしさ。イタリア・オペラの歴史から現代の日本のオペラ事情まで、総合芸術としてその魅力を語り尽くします。誌上でその楽しみを味わった後は、ぜひ劇場へ足を運んでみてください。 |
 |
| <連載> |
KEIO MONO MUSEUM28
曾禰中條建築事務所 三田校舎基本設計鳥瞰図(解説 都倉武之)
|
|
大久保忠宗 |
|
大澤輝嘉 |
| |
|
| <その他> |
演説館 |
筒井大和 |
塾員クロスロード |
加藤雅敏、高川 航 |
| Researcher's Eye |
日高千景、齋藤英胤、徳久 悟 |
| 執筆ノート |
『諜報の天才 杉原千畝』(白石仁章 著)
『朗朗介護』(米沢富美子 著)
『デザインの骨格』 (山中俊治 著) |
| 社中交歓(城) |
下高原正人、水野衛子、田代大輔、時国安依 |
| <追想> |
| 蝶ネクタイの平良先生 西川理恵子
|
| <KEIO Report> |
| 公開講座「被災ミュージアム支援と危機管理対策」に大きな反響 鈴木隆敏
|
| <矢上キャンパス内の発掘調査について> |
| 安藤広道 |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|