慶應義塾機関誌
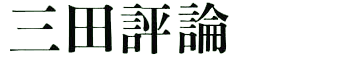
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
| |
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
高齢社会のなかの住宅問題 |
| |
少子高齢化が進むにしたがって、特に都市部、郊外での日本人の「住まい方」が急激に変化しています。郊外での空き家の激増、超郊外や地方への住みかえなど、最近の高齢者の「住まい方」の問題を人口構造の変化、介護政策、住宅市場の視点から多角的にみていく特集です。 |
| |
| ◆座談会 |
| これからの「高齢期の住まい方」を考える |
|
大垣 尚司 |
|
立命館大学大学院法学研究科教授、金融・法・税務研究センター長 |
和泉 洋人
|
|
内閣官房地域活性化統合事務局長 |
大江 守之 |
|
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
駒井 正晶 |
|
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
| <関連記事> |
| 高齢社会におけるリバースモーゲージの役割 |
|
隅田和人
金沢星稜大学経済学部准教授・塾員
|
| 少子高齢社会と郊外ニュータウン |
藤井多希子
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)・塾員
|
|
|
|
| |
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
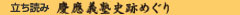 |
|
桃介は、農家岩崎紀一の次男として、慶應四(明治元)年五月六日現在の埼玉県比企郡吉見町荒子に生まれた(現在、東吉見郵便局前に「生誕の地」の立て札がある)。慶應義塾に在学中、留学させてもらうことを条件に福澤先生の次女房の婿養子となり、福澤姓となった。彼は、日本各地の豊富な水力を利用した電源開発を行い、その電力を利用した多くの殖産事業に関わり、「日本の電力王」「財界の鬼才」と称される人物である・・・
|
|
|
| |
| 次号予告 |
| 三田評論2010年6月号 No.1135 |
◆特集◆
SFC20周年 |
|
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <三人閑談> |
| 古地図を辿る |
| 鈴木 純子(日本国際地図学会評議員) |
| 井口 悦男(慶應義塾名誉教諭) |
太田 弘 (慶應義塾普通部教諭) |
|
| 伊能忠敬が作成した「伊能図」をはじめ、古地図にはその時代の文化や生活が滲み出ていて味わい深いものがあります。また、近代国家形成の歩みを辿る意味でも地図は欠かせないものです。「古地図」を長年研究してきた方々が、日本の地図保存の問題点まで視野に入れ、熱く語り合います。 |
 |
| <話題の人> |
| 公益資本主義にもとづく実学教育のすすめ |
| |
|
|
原 丈人さん
(デフタ パートナーズグループ会長・塾員) |
| |
インタビュアー
国分良成(慶應義塾大学法学部長) |
| |
|
| 現在アメリカを中心に主流である「金融資本主義」に対して、「会社は社会のためにいかに役立つか」という「公益資本主義」の考え方を提唱する原さんに、バングラデシュでの最先端技術を使った実践例を交えてお話しいただきました。原さんの公益資本主義の実現に向けた熱い思いは、教育にまで広がり、これからの日本を考える上で示唆に富んでいます。 |
| |
|
| <巻頭随筆 丘の上> |
岡晴夫、佐伯胖、酒井忠久、西室泰三
|
| |
|
| <連載> |
KEIO MONO MUSEUM16 小泉信三の双眼鏡 (解説 都倉武之)
|
|
加藤三明 |
|
大久保忠宗 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|