慶應義塾機関誌
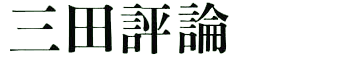
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
|
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
| |
「教養崩壊」が話題に上る現在、「教養」とは一体なにか、大学は「教養」を教えられるのか、との問いは重要なことであるように思います。教養形成のあり方、進化するメディアとの関わり、専門教育との関係をめぐる議論とともに、明治期の慶應義塾の学問の独自性についての記事などが並び、多くの切り口から「教養」について考えていきます。 |
| |
| ◆座談会 |
| 大学は「教養」を教えられるのか |
|
日比谷潤子 |
|
国際基督教大学学務副学長・教養学部教授 |
苅部 直
|
|
東京大学法学部教授 |
鷲尾 賢也 |
|
元編集者・塾員 |
横山 千晶 |
|
慶應義塾大学法学部教授・教養研究センター所長 |
松浦 良充 |
|
慶應義塾大学文学部教授 |
| <関連記事> |
| アメリカの大学教育のなかの「教養」 |
|
坂本辰朗(創価大学教育学部長・塾員)
|
慶應義塾は「洋学」の何を継承したか--福澤諭吉の学問観と「文明」
|
米山光儀(慶應義塾福澤研究センター所長、慶應義塾大学教職課程センター教授) |
教養、「教養」、何が教養
|
戸瀬信之(慶應義塾大学経済学部教授) |
|
|
|
| |
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
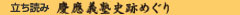 |
|
『西洋事情』の「博覧会」
今年は、5月から10月まで上海で万国博覧会が開かれている。世界最初の万国博覧会は1851年にロンドンで開催された「グレート・エキシビション」であるが、1862年に再びロンドンで開かれた「インターナショナル・エキシビション」には文久2年の遣欧使節、従ってその一員の福澤先生も訪れていた・・・
|
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <最高裁判所判事に就任> |
| 「岡部喜代子さんの横顔」 |
| 佐貫葉子 |
 |
| <三人閑談> |
| 上海 今昔 |
| 榎本泰子(中央大学文学部教授) |
| 福澤真由美(日本テレビ報道局記者・塾員) |
田島英一(慶應義塾大学総合政策学部教授) |
|
| 今年は5月から上海で万博が始まり、多くの日本人も彼の地を訪れています。かつては租界があり、日本との関係も深かった大都市・上海の歴史は、他の中国の都市と比べ格段に変化に富み、波乱の中で現在も独自の変化を遂げているようです。上海にゆかりの深い方々が、活気に満ちたその街の「今」と「昔」の空気を伝えます。 |
 |
| <巻頭随筆 丘の上> |
中村 達、中村時広、林 望、吉武泰俊 |
| |
|
| <講演録> |
『福翁自伝』の成り立ちについて--晩年の福澤諭吉 |
松崎欣一 |
| |
|
| <連載> |
KEIO MONO MUSEUM18
泉鏡花の水晶の兎 (解説 都倉武之)
|
|
山内慶太 |
|
大久保忠宗 |
| |
|
| <その他> |
塾員クロスロード |
藤本裕子、森田貴英 |
| Researcher's Eye |
土居信英、池田年穂 |
| 執筆ノート |
『ローマが風景になったとき--西欧近代風景画の誕生』
/小針由紀隆
『台湾人生』
/酒井充子
『鳥脳力--小さな頭に秘められた驚異の能力』
/渡辺 茂 |
| 社中交歓(瓜) |
野並直文、木佐貫幸伸、安藤寿康、相場博明 |
練習は不可能を可能にす--塾野球部優勝報告(
前島 信) |
| <追想> |
| 大西祥平先生の思い出 |
勝川史憲 |
中川純男君を悼んで西脇与作
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|