慶應義塾機関誌
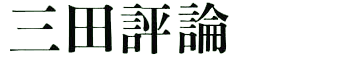
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
| |
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
介護保険導入10年 |
| |
2000年に介護保険制度が導入されてから10年目となる本年、その歩みを検証し、これからよりよい高齢社会を築くために何が必要かを考える特集です。介護を必要とする人々が急速に増えている現在、かつての「子どもが親の面倒をみる」という日本人の意識の変化や、財政的な負担を誰が負うのかといった問題などについて様々な角度から討議します。 |
| |
| ◆座談会 |
| 将来を見据えて介護保険を検証する |
|
ジョン・C・キャンベル |
|
ミシガン大学名誉教授、東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員 |
高野龍昭
|
|
東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科専任講師 |
大塚宣夫 |
|
医療法人社団慶成会理事長 |
鈴木康裕 |
|
厚生労働省老健局老人保健課長 |
池上直己 |
|
慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授 |
|
|
|
| <関連記事> |
| 介護保険と介護市場――これまで・現状・未来 |
田中 滋
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
|
|
|
|
| |
| 『慶應義塾史事典』を読んで |
| |
大学史研究の金字塔(佐藤能丸)
塾史の精髄を一冊に(紀田順一郎)
日本近代医学史も息づく事典(比企能樹) |
|
|
| |
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
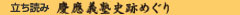 |
|
 |
文久2(1862)年の遣欧使節団の一員として福澤先生がサンクトペテルブルクに滞在したのは、陽暦では8月から9月にかけての気候も穏やかな時期であった。今号では、日本人も良く訪れるエルミタージュ美術館周辺の史跡を巡ってみたい・・・
|
|
|
|
| |
| 前号紹介 |
| 三田評論8-9月合併号 No.1126 |
◆特集◆
現代塾生事情
|
| ◆寸描 前号について |
昭和20年8月の長崎で最も多感な時季を迎えようとしていた三浦冨美子君は、「64年を経て、蝉しぐれはなお私にとり、苛酷な体験の暗喩である。」と書き、《少女われ夢のノートを捨ておきて逃げまどいたり炎(ひ)の渦のなか》と歌う。米沢富美子君は、新著『猿橋勝子という生き方』の執筆ノートを、「諸刃の剣である科学の功と罪を科学者こそが語り続けなければならない・・・ |
|
|
 |
| |
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <三人閑談> |
| 浮世絵の魅力 |
| 渡辺保(演劇評論家) |
| 渡邊章一郎(渡邊木版美術画舗代表取締役) |
| 内藤正人(慶應義塾大学文学部准教授) |
|
| 世界でも有数の質を誇る慶應義塾蔵「高橋誠一郎浮世絵コレクション」。この秋に展覧会が開かれるのを期に、浮世絵の魅力に迫ります。もともと女性が少ない江戸という街であったからこそ「美人画」が流行り、そのうち女性のあいだでブロマイドとしての「役者絵」が大ブームとなった……。そんな背景を知ると一層鑑賞が楽しくなること請け合いです。 |
 |
|
| <巻頭随筆 丘の上> |
小田 豊、二宮 寛、二村徳子、吉松 隆 |
| |
|
| <講演録> |
演劇人・高橋誠一郎――観客として・先導者として |
犬丸 治 |
| |
|
| <連載> |
KEIO MONO MUSEUM9 「中等部の歌」楽譜
|
|
山内慶太 |
|
大久保忠宗 |
| |
|
| <その他> |
塾員クロスロード |
|
| Researcher's Eye |
矢野恵美、衛藤憲人、堀田一吉 |
| 執筆ノート |
高橋潤二郎、鷲見誠一
清水 浩
|
| 社中交歓(重(じゅう)) |
別府 允、山本恒
菅野利郎、吉川嘉一郎 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|