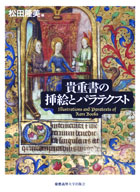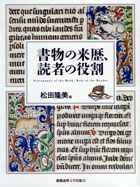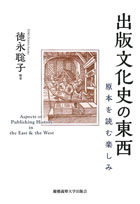・松岡正剛さんが当社のシリーズ「世界を読み解く一冊の本」を「セイゴオほんほん」でご紹介くださりました。
・シリーズ「世界を読み解く一冊の本」(略して「せかよむ」)のパンフレット(完結版)はこちら!
・慶應義塾大学出版会のnoteでは、「せかよむ」を試し読みいただけます。
・【動画】シリーズデザインを手掛けたグラフィックデザイナー・岡部正裕さんのインタビュー
・本シリーズの最新情報は当サイトでお知らせします。ご期待下さい!


・松岡正剛さんが当社のシリーズ「世界を読み解く一冊の本」を「セイゴオほんほん」でご紹介くださりました。
・シリーズ「世界を読み解く一冊の本」(略して「せかよむ」)のパンフレット(完結版)はこちら!
・慶應義塾大学出版会のnoteでは、「せかよむ」を試し読みいただけます。
・【動画】シリーズデザインを手掛けたグラフィックデザイナー・岡部正裕さんのインタビュー
・本シリーズの最新情報は当サイトでお知らせします。ご期待下さい!
人類は、世界の真理を収めるような器としての書物を多数生み出し、時代や文化の違いを超えて脈々と読み継いできました。
このシリーズは、「書物は一つの宇宙である。世界は一冊の書物である」をキーワードに、〈世界〉を規定し、人々の生き方を示す宗教書や、言葉を整理し〈世界〉の見方を示す辞典、〈世界〉を知の迷宮へと誘う奇書、知へのアクセスを制限し〈世界〉を限定する焚書など、世界の名著のなかでも、とりわけ「本について問題提起をする」、今読むべき古今東西の古典・新古典を厳選し、書物史、文学研究、思想史、文化史などの第一人者が、縦横無尽に読み解きます。
その際、特に大事にしたのが、その作品世界と社会や人間に向けられた眼差しをわかりやすく解説するのみならず、そもそもその書物がいかにして誕生し、読者の手に渡り、時代を超えて読み継がれていったのか、翻訳されて異文化にも受け入れられていったのかを書物文化史の視点から考えるという点です。書物の魅力を多角的に捉えることで、その書物がいかにして〈世界を読み解く一冊の本〉としての位置を文化のなかに与えられるに至ったのかを、書物を愛するすべての読者諸氏に向かって、深く丁寧に掘り下げることを大切にしました。
時に、聖典として崇められ、時に、焚書や発禁をうけた書物の運命は、つねに私たち人間とともにありました。私たちにとって、本とはいったい何なのでしょうか? 今後、本はどのような運命を辿っていくのでしょうか? その問いを、〈世界を読み解く一冊の本〉を紐解くことによって一緒に考えてみませんか。
慶應義塾大学出版会編集部

古今東西の古典・新古典を、もっとおもしろく、深よみ・深ぼりする。
人々の生き方を示す宗教書から、知の迷宮へと誘う書、
時代に警鐘をならすディストピア小説まで、
「本について問題提起をする」今読むべきベストセラー10作を厳選。
名著が〈世界〉や人をどう描き、現代にどんなメッセージを発しているのか、
第一線・気鋭の執筆陣が、縦横無尽にわかりやすく読み解く。
名著がどのように成立し、読み継がれるようになったのかを、
書物文化史の観点から辿る。
せかよむ★キャット

せかよむ★キャット
あたまの模様は世界地図。
好奇心にみちあふれたキラめく瞳で、 今日も古今東西の本をよみあさる!
書物は一つの宇宙である。世界は一冊の書物である。事実、人類は世界の真理を収めるような書物を多数生み出し、時代や文化の違いをこえて営々と読み継いできた。
本シリーズでは、作品がもつ時空をこえる価値を明らかにするのみならず、作品が一冊の書物として誕生し、読者を獲得しつつ広がっていったプロセスにも光をあてる。書物史、文学研究、思想史、文化史などの第一人者が、古今東西の古典を対象として、その作品世界と社会や人間に向けられた眼差しをわかりやすく解説するとともに、そもそもその書物がいかにして誕生し、読者の手に渡り、時代をこえて読み継がれ、さらに翻訳されて異文化にも受け入れられたのかを書物文化史の視点から考える。
書物の魅力を多角的にとらえることで、その書物がいかにして世界を読み解く一冊の本としての位置を文化のなかに与えられるに至ったかを、書物を愛する全ての読者に向かって論じてゆく。
松田隆美(慶應義塾大学教授、シリーズアドバイザー)
森のなか、ほの暗い、少し角張った不思議な影が揺らいでいるのに気づきませんでしたか?
ブナの大樹の下には涼やかな風が舞っていて、そこに影のような小さな物体が白い紙片をはためかせていました。永遠の太陽が、梢の隙間から光の帯を差しかけていました。人類の歴史の陽だまりに長いあいだ置かれてきたその黒い影は、私たちに自らの存在を知らせることを止めませんでした。ときどき雨に濡れ、露を浴び、落葉に覆われ、ページのなかに木食虫が秘密の坑道をあけても、その影は静かに、たしかに、語りつづけてきました。ことばへの信があるかぎり。ことばをのせる器としての、おのれの身体が脈打ちつづけるかぎり。
そうです、このほの暗い影こそが書物であり、私たち人類が生み出してきた世界知が宿る、生命そのものの深い陰影の証しです。
今福龍太(東京外国語大学教授)

| 2018年10月刊行 |
| 大槻文彦 『言海』 辞書と日本の近代 |
|---|
| 安田敏朗(一橋大学准教授) |
| 国語学者、大槻文彦が明治期に編纂した日本初の近代的国語辞典『言海』。大槻は『言海』を通して世界をどのように切りわけようとしたのか。辞書が社会的に果たした役割とともに描き出す。 詳細はこちら |
| 『言海』 1891年刊行(日本) |

| 2018年11月刊行 |
| 『クルアーン』 神の言葉を誰が聞くのか |
|---|
| 大川玲子(明治学院大学教授) |
| 極めて難解とされるイスラームの聖典『クルアーン』。ではどう読めばよいのか? 聖典を読む困難と楽しさを、丁寧に解説。信徒のみならず、人類にとっての「聖典」となる可能性を問う。 詳細はこちら |
| 『クルアーン』 7世紀成立(アラビア半島) |

| 2019年2月刊行 |
| 『西遊記』 妖怪たちのカーニヴァル |
|---|
| 武田雅哉(北海道大学教授) |
| 映画やマンガにリメイクされつづける『西遊記』は子ども向けの本ではない? 中国の誇る〈神怪小説〉のなりたちと伝播を、妖怪たちの目線から語りつくす。 詳細はこちら |
| 『西遊記』 16世紀成立(中国) |

| 2019年4月刊行 |
| チョーサー 『カンタベリー物語』 ジャンルをめぐる冒険 |
|---|
| 松田隆美(慶應義塾大学教授) |
| 英文学の礎を築いた「英詩の父」チョーサー。多種多様なジャンルを革新的に問い直し、物語文学の枠組みを拡張した、中世を代表する傑作のダイナミズムを描く。 詳細はこちら |
| 『カンタベリー物語』 1388年頃~1400年制作(イギリス) |

| 2019年8月刊行 |
| 『百科全書』 世界を書き換えた百科事典 |
|---|
| 井田尚(青山学院大学教授) |
| 啓蒙の世紀を象徴するフランス初の本格的百科事典は、どのように編まれたのか。森羅万象を体系的かつ批判的に記述しようとした壮大な試みを明らかにする。 詳細はこちら |
| 『百科全書』 1751~72年刊行(フランス) |

| 2022年4月刊行 |
| オーウェル 『一九八四年』 ディストピアを生き抜くために |
|---|
| 川端康雄(日本女子大学教授) |
| 全体主義国家によって分割統治された近未来世界を描く、世界的ベストセラー。「ポスト真実」の時代を先取りしたディストピア小説の世界を探る。 詳細はこちら |
| 『一九八四年』 1949年刊行(イギリス) |

| 2022年4月刊行 |
| 空海『三教指帰』 桓武天皇への必死の諫言(かんげん) |
|---|
| 藤井淳(駒澤大学教授) |
| 日本思想の最高峰・空海が二十四歳のときに物した出家宣言書。仏教・儒教・道教という三つの〈宗教〉をめぐる対話が戯曲形式で繰り広げられる、比較〈宗教〉論とも言える本作に、若き空海の出発点を探る。 詳細はこちら |
| 『三教指帰』 797年成立(日本) |

| 2021年4月刊行 |
| エーコ 『薔薇の名前』 迷宮をめぐる〈はてしない物語〉 |
|---|
| 図師宣忠(近畿大学准教授) |
| 記号論の大家エーコによる問題小説。中世イタリアの修道院で起きる連続殺人事件の謎と迷宮構造の文書館に収められた一冊の書物の存在をめぐる遠大な物語世界にエーコがしかけた知のたくらみを繙く。 詳細はこちら |
| 『薔薇の名前』 1980年刊行(イタリア) |

| 2019年12月刊行 |
| ボルヘス 『伝奇集』 迷宮の夢見る虎 |
|---|
| 今福龍太(文化人類学者・批評家) |
| 幻想小説の巨匠ボルヘスによる「バベルの図書館」「八岐の園」「死とコンパス」など名作一七篇を収録した短編集。現実と虚構の境界を往来する、書物という迷宮を、ボルヘスと共に、ボルヘスになり切って読み解く。 詳細はこちら |
| 『伝奇集』 1944年刊行(アルゼンチン) |

| 2020年9月刊行 |
| 『旧約聖書』 〈戦い〉の書物 |
|---|
| 長谷川修一(立教大学准教授) |
| 旧約聖書はいかにして生まれたのか。なぜそれは人類のベストセラーとなりえたのか。旧約聖書形成の背後に潜む激動の歴史と対比させつつ、著者たちが繰り広げた思想史上の戦いを追いかける。 詳細はこちら |
| 『旧約聖書』 2世紀成立(イスラエル) |