慶應義塾機関誌
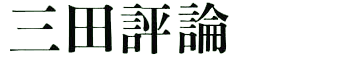
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
| |
|
| |
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
|
大学の技術と知財から、いかに新産業を創出させていくか。科学技術立国を目指す日本の課題であるとともに慶應義塾の課題です。昨年末、慶應義塾が本格的なベンチャーキャピタルを設立したことを機に、大学発ベンチャーの現況とその支援について展望します。産業化を生むシステムをキャンパスのなかから生みだすために何が必要か。その挑戦が今始まっています。 |
| |
| |
| 〈座談会〉慶應ベンチャーキャピタルの船出 |
| |
村口和孝(日本テクノロジーベンチャーパートナーズ(NTVP)代表・塾員)
塩野 誠(株式会社経営共創基盤パートナー・取締役マネージングディレクター・塾員)
山岸広太郎(株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)代表取締役社長・塾員)
菱田公一(慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授・塾員)
|
|
| |
| 〈関連記事〉 |
大学技術の民間移転と大学教育
岡田正大(慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授)
|
| |
山形県鶴岡市に花開く「異端と先導」の福澤精神
冨田 勝(慶應義塾大学先端生命科学研究所所長)
|
| |
SFCにおける新事業創造への取り組みについて
廣川克也
(湘南藤沢キャンパスインキュベーションマネージャー、一般財団法人SFCフォーラム事務局長)
|
| |
| |
|
|
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <話題の人> |
| 読売巨人軍監督に就任 |
| |
|
 |
高橋由伸さん
(読売巨人軍監督・塾員) |
| |
インタビュアー
後藤寿彦(慶應義塾体育会野球部元監督、三田倶楽部会長) |
| |
|
|
昨シーズン限りで現役を引退し、巨人軍の監督に就任した高橋由伸さん。現在行われている春季キャンプでは、その一挙手一投足に大きな注目が集まっています。18年間の現役生活にピリオドを打つという決断、指揮官として臨む最初のシーズンへの意気込み、そして体育会野球部での日々について、じっくり語っていただきました。 |
| |
|
 |
| <三人閑談> |
| 寝台列車よ永遠に |
堺 正幸(元フジテレビアナウンサー・塾員)
石破 茂(衆議院議員、国務大臣(地方創生・国家戦略特別区担当)・塾員)
小川克彦(慶應義塾大学環境情報学部教授) |
|
| 3月の「カシオペア」定期運航終了で、ますます寂しくなってしまった日本の寝台列車事情。しかし寝台列車への思いは愛好家のなかで生き続けています。寝台列車を愛してやまない三人が語り合った1時間、その思いは過去から未来へと夜空を駆け抜けていきました。
|
| |
| <連載> |
|
大久保忠宗 |
| 義塾を訪れた外国人 第3回 ネルー |
山本信人 |
|
| |
| <新慶應義塾豆百科3> |
| グーテンベルク聖書 |
|
| |
| <写真に見る戦後の義塾3> |
| 旧図書館の風景 |
赤木完爾 |
|
|
|
| <講演録> |
福澤諭吉とギャレット・ドロッパース
──大学部開設百二十五年に寄せて |
池田幸弘 |
|
|
|
| <演説館> |
未来の学校を体現する学舎へ
──ふたば未来学園高での取り組み |
南郷市兵 |
|
|
| <その他> |
丘の上 |
石井栄一、西野鷹志、平井俊邦、萬 知子 |
塾員クロスロード |
池田 昇 |
| Researcher's Eye |
西野純也、久保田義顕 |
| 執筆ノート |
『東横歌舞伎の時代』
上村以和於
『皇室一五〇年史』
浅見雅男(共著)
『シンガポールの光と影──この国の映画監督たち』
盛田 茂
『アジアの文化遺産──過去・現在・未来』
鈴木正崇(編)
|
| 社中交歓(豚) |
本城和子、南波克行、冨士原圭一、奥田暁代 |
|
| <震災から5年> |
| 慶應義塾南三陸プロジェクトの活動の今
|
長沖暁子
|
| 東北の子どもたちの学習支援を続けて
|
鈴木健大
|
|
|
|
| <KEIO Report> |
| 慶應義塾ニューヨーク学院(高等部)創立二五周年を振り返って |
山崎敬夫 |
| |
|
| <時は過ぎゆく> |
| 前田監督を悼む |
西岡浩史 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|