慶應義塾機関誌
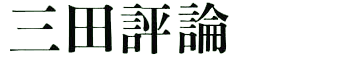
明治31年3月創刊(毎月1回1日発行)
発行:慶應義塾 編集人:慶應義塾広報室長 編集・制作:慶應義塾大学出版会
|
|
 |
2018年6月号表紙 |
|
                 |
 |
| |
|
| 毎月1回1日発行 |
| 税込価格:451円(本体 410円) |
| 定期購読:4,700円(税・送料込) |
| 在庫あり |
 |
 |
|
|
 |
|
| |
| ◆特集 |
歴史人口学の射程 |
| |
2009年度の文化勲章を速水融名誉教授が受章されたことを受けて、「歴史人口学」という学問の歩みと、様々なこれからの可能性について分かりやすく解説する特集です。人口減少社会となり、家族のあり方が問われている現在、人口という物差しで歴史を顧みることが、大きな示唆を与えてくれることがわかります。 |
| |
| ◆座談会 |
| 歴史人口学の継承と発展へ向けて |
|
速水 融 |
|
慶應義塾大学名誉教授 |
友部謙一
|
|
大阪大学大学院経済学研究科教授・塾員 |
磯田道史 |
|
茨城大学人文学部准教授・塾員 |
鬼頭 宏 |
|
上智大学経済学部教授・塾員 |
|
|
|
| <関連記事> |
| 小さな異文化交流――速水融教授と実証経済学派 |
尾高煌之助
|
経産研究所編纂主幹・塾員
|
| 歴史人口学と社会経済史 |
斎藤 修
|
一橋大学名誉教授・塾員
|
| 不肖の弟子から見た恩師 |
浅見雅男
|
編集者、近代史研究者・塾員
|
|
|
|
| |
|
|
| 慶應義塾維持会 |
母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された一世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。 |
|
|
| |
|
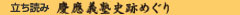 |
|
2月3日は福澤先生の御命日である。毎年この日は、先生の墓所の麻布山善福寺に、早朝から夕方まで墓参に訪れる塾生、塾員の列が絶えることはない。福澤先生の墓所が善福寺に移ったのは、昭和52年5月のことで、それまでは上大崎の常光寺にあった・・・
|
|
|
|
|
 |
|
|
| ◆その他の企画 |
| <講演録> |
| 高橋誠一郎生誕125年記念連続講演会 |
高橋誠一郎からみた福澤諭吉
猪木武徳(国際日本文化研究センター所長) |
高橋誠一郎と戦後の文部行政
佐藤禎一(東京国立博物館名誉館長、元ユネスコ代表部特命全権大使) |
文学者としての高橋誠一郎
渡辺 保(演劇評論家・塾員) |
|
| 2009年に生誕125年を迎えた高橋誠一郎についての連続講演会の講演録を一挙に3本掲載。猪木武徳さん、佐藤禎一さん、渡辺保さんと各界の一線でご活躍されている方々が、直接、また書物から感じ取った高橋誠一郎の姿をいきいきと語ります。 |
 |
| <話題の人> |
| 大宮司として伊勢神宮の式年遷宮を推進する |
| |
|
 |
鷹司尚武さん (神宮大宮司) |
| |
インタビュアー
竹内明彦 |
| |
|
| NEC系列企業の経営者から、2007年に伊勢神宮の大宮司に就任された鷹司さん。現在2013年の式年遷宮に向けて様々な準備を行っている最中に、式年遷宮1300年の意味、神宮の伝統文化を伝える重要な役割について大変興味深いお話しを伺いました。
伊勢の神宮の歴史とその役割について、理解が深まること請け合いです。
|
| |
|
|
| <巻頭随筆 丘の上> |
浅野加寿子、桜井 武、富塚陽一、伴 充弘 |
| |
|
| <演説館> |
鉄道コンテナ輸送50年を迎えて |
岩沙克次 |
| |
|
| <連載> |
KEIO MONO MUSEUM13 福澤が持ち帰った米国人少年写真
解説 都倉武之
|
|
山内慶太 |
|
大久保忠宗 |
| |
|
| <その他> |
塾員クロスロード |
松坂晴恵、鳥山雄司 |
| Researcher's Eye |
柳瀬 昇、岩丸有史、奈良龍乗 |
| 書評 |
『明治人の観た福澤諭吉』
(伊藤正雄編)/山田博雄
|
| 執筆ノート |
佐々木秀一、脇田 玲
|
| 社中交歓(短い) |
藤原千恵子、依田龍一
山下大輔、有元眞理子 |
| 追想 |
倉澤康一郎先生を偲んで(宮島 司)
藤田弘夫先生を想う(岩波敦子) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|