No.1230(2019年2月号)
特集
No.1230(2019年2月号)
特集
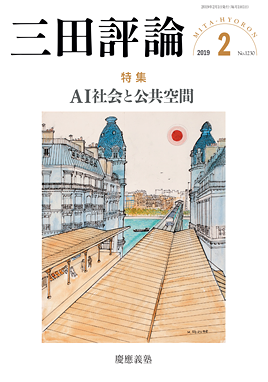
三田評論
2019年2月号表紙
「KEIO Report」の頁で新旧の見事な二企画が報告されている。まずは近未来型の「KGRI」(安井正人)。塾長も「年頭の挨拶」で大きく取り上げ、特集「AI社会と公共空間」のテーマでもある。座談会5名中3名がKGRIのメンバーなのだ。特集は「公共性」と「AI」とを重ね合わせ、微妙な境界領域を論じて興味深い。たとえば「公共性」の「自由」と「受忍」(大屋雄裕)は、本誌巻頭グラビア写真に「映ってしまった」(笑)、大勢の塾員、塾生に連想が赴く。座談会の暗黙の合意概念「人起点」は賛成。でもハーバーマスの不滅の名著『公共性の構造転換』に誰か言及して欲しかったなあ。かたや近過去型企画と呼べるのが「慶應義塾と戦争」(都倉武之)。都倉氏が紹介する遺書「明日は自由主義者が一人この世から去って行きます」(戦没塾生上原良司)を「人起点」にして、近未来と近過去をつなぎたい。ある記事への応答が別な頁に用意されているのは嬉しい。
鷲見洋一

AIについての話題を見かけない日がない今日ですが、AI技術がITネットワークと結びついた際に生まれる社会へのインパクトは想像を超えるものがあります。圧倒的な利便性の一方、個人情報流出や監視社会化への不安を感じる方もいるでしょう。「AIによる人の選別」がリアルに語られるようになった現在、社会はそれにどう応えていくのかを考える特集です。


竹本勝紀さん
銚子電気鉄道株式会社代表取締役社長・塾員
地方都市の交通インフラを支える地方私鉄は、沿線人口の急速な減少や高齢化で経営が難しくなっているところも多数あります。銚子電鉄もこの十数年、度重なる経営危機を迎え、それを「ぬれ煎餅」などの販売や車両の“エンタメ”化で乗り越えてきました。その陣頭指揮を執ってこられた竹本さんによる破天荒な「電鉄経営裏話?」です。

「あの人の声いいね」、人はどうしてそう思うのでしょう? 「いい声」「通る声」「正しい声」など、その発声の仕組みはどのようになっているのか。人は意外と声を気にします。そして、ほめられると嬉しい。そんな自信の源にもなりうる、「声」の秘密に迫る閑談です。

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。
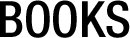 慶應義塾大学関連の書籍
慶應義塾大学関連の書籍