No.1228(2018年12月号)
特集
No.1228(2018年12月号)
特集
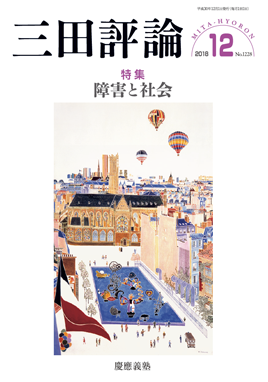
三田評論
2018年12月号表紙
遠いものを結ぶ、意外なもの同士を重ねる。名言、卓見の秘訣である。まずは故浅利慶太氏の基本姿勢。「今、ご自身が語ったことを全く別の角度から反論される」(吉田智誉樹)。障害者差別解消法の「みんなちがってみんないい」(大胡田誠)こそまさにそれ。障害者の社会参加を野球のメジャーリーグにたとえる卓抜な発想(大胡田誠)も同じ。ハイブリッドのお手本のような「みなし雇用」(中島隆信)の提言。昨年パリで「ウーバータクシーは本当に便利だ」と痛感したが、帰国後に疑問視するようになり、今回の「ウーバーで考えるシェアリングエコノミーの本質」(田邉勝巳)で今一度揺さぶられるという快い体験も同じ。きわめつけは大火傷の小泉信三先生が顔を映せないようにと、朝食の味噌汁の椀を箸で濁らせて差し出した看護婦と先生とのやりとり(「戦時に小泉信三先生を看護して」加藤ミチ)。ほとんどギリシア神話の崇高さに達する凄い話ではないか。
鷲見洋一

障害の「医学モデル」から「社会モデル」への転換が言われ、社会の側から障害のある方への配慮がより求められるようになっています。社会参加への根本とも言える「雇用」の問題から、ノーマライゼーションの考え方、最近ますます注目されるパラ・スポーツまで、障害当事者の方の声も反映した特集です。

本年は慶應義塾に看護養成所が設立され、看護教育が始まって100年の年。その間の最大の苦難は太平洋戦争時、信濃町の施設の6割が焼失した空襲でした。一人の死者も出さずに患者を避難させた当時の看護婦の方々の中には、三田の空襲で大火傷を負って入院した小泉信三塾長の看護にあたった方がいました。慶應義塾の貴重な歴史を記したインタビューです。
インタビュアー:
小池 智子(看護医療学部准教授)
山内 慶太(看護医療学部教授)
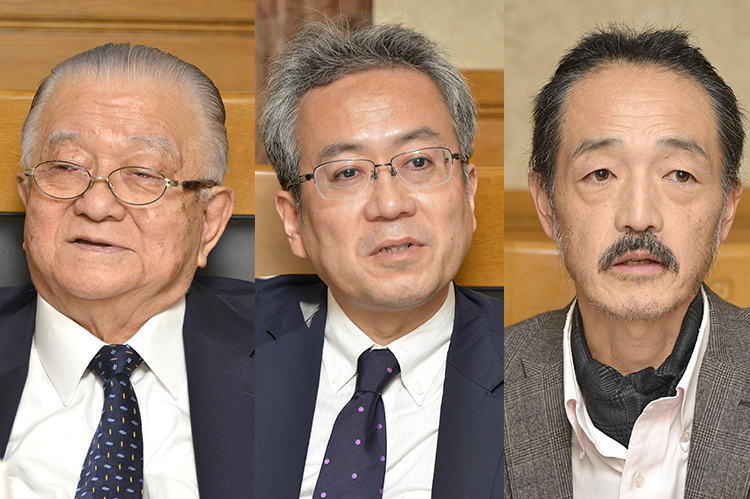
劇団四季の設立者で、戦後の日本の演劇界に大きな足跡を残した浅利慶太さん。この七月に逝去された浅利さんは、戦後間もない慶應義塾高校で演劇を始め、晩年まで慶應義塾への愛情を持ち続けていた方でした。ゆかりの方々による追悼の閑談です。

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。
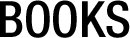 慶應義塾大学関連の書籍
慶應義塾大学関連の書籍