�u�l�����T���\�V���s�w�h�̗������i�v���t�B�[���j�\�v
��P�W��
�ˋ�ҏW��c�@�u�l�����T���v�̂���܂łƂ��ꂩ��
���ˋ�ҏW��c
�ҏW��H�F�搶�A���ז��������܂��B
����K�F����ɂ��́B�����J���������A���肪�Ƃ��������܂����B
H�F�Ƃ���ŁA�ǂ��������̐����Łu�ˋ�ҏW��c�v�Ȃ�ł����H
K�F����B�����ς��������C�����Ȃ��ł��Ȃ��̂����ǁA�u���k��v�͐V���s�w�h�̂��ƌ|�Ƃ������ׂ��X�^�C��������A��x���炢�����ł���Ă݂�̂��K�v���ȁA�Ǝv�����B
H�F�Ȃ�قǁB�Ō�ɍ��k����ڂ��Ă܂Ƃ߂�A�Ƃ�����i�����Ȃ��Ȃ��ł���ˁB
K�F�����B���Ƃ��ΌK�����v�̋��������Ȃ�w���\�[�����x�i1951�j��w���w���_�̌����x�i1967�j�����k����ڂ��Ă���B������̂��̂����k��I�����B�u���w��v�Ƃ��ʂɋ����������Ƃ͌K�����g���w�E���Ă���i�A�ڑ�2���j�B
H�F�����������k��͘_�d���̖��ߑ��Ƃ��Ďn�܂����Ƃ����Ă��܂���ˁB������w�p�_�W�Ɏ������̂́A��͂����I�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�V���s�w�h���ŏ��ł͂Ȃ��ɂ���A�X�^�C���Ƃ��Ċm���������킯�ł�����B
K�F����͂��肻�����ˁB�������A�o�ŎЂ���������}�����B�V���s�w�h�̖ʁX�����f�B�A�̒������������Ƃ�����A���k��ɏ��i���l���������B��������Ę_�W��ʎY�ł����B�ߔN�A�w�p�_�W���o�ł���̂ɂ��炭��J���邱�Ƃ������̂ŁA�u���̊��Ƃ������A�����܂������肾�B
H�F���������ʂ�ł����A����������s�͂ЂƂ܂��u���āA�u�l�����T���v�̘b��i�߂܂��傤�B
K�F�����ł��ˁB
���J���L�O���̉�
H�F�Ƃ���ŁA�u�l�����T���v���O�g���w10�{1�x���琔���Ă��傤��10���N���}���܂��B��N����P�N�Ԃ̋x�ڂ��o�Ă��悢�惊�X�^�[�g����킯�ł����A�ӋC���݂̒��͂������ł��傤���H
K�F���ꂪ�˂�……�B
H�F�����Ȃ艓���ڂɂȂ�Ȃ��ʼn������i�{�j�B
K�F����A�������A�C�f�A�͂����B���낢��B
H�F�Ӂ[��B���Ƃ��H
K�F�܂��A�u�l�����͕Ď����j���邩�H�\���邢�͊J���L�O���̉��\�v�Ƃ����l�^�B
H�F�������ɁA1929�N�ݗ��̓��������w�@���s���������琔���č��N�i2017�j��88�N�ځB�Ď��ɂ�����܂����A�ł��A�����̐l���w���߂���S����l����ƁA�f���ɏj���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��A�Ƃ����킯�ł��ˁB
K�F����������Ȃ��ǁB������A����1929�N���N�_�ɂ��鐔���������������������̂��A�Ƃ�����肪����B
H�F�ƁA�����܂��ƁB
K�F�l�����̊J���L�O�s����11���J�ÂȂ���ǁA����͑g�D�̐ݗ��ł͂Ȃ������̊����ɂ��Ȃ�ł���B���������w�@���s�������̐ݗ����ꂽ1929�N4���ł͂Ȃ��A�����̏v�H����1930�N11�����N�_�B���̐��������炷���1931�N11�����n���P���N�ŁA���������A���̔N�Ɂu����N�L�O�u����v�����{���Ă���B���̐��������炷��ƁA���N��87�N�ڂŁA�܂��Ď��ł͂Ȃ����ƂɂȂ�B
H�F�Ȃ�قǁA�ǂ����ŃY���Ă��܂����Ƃ����킯���B��̂ǂ��ŃY�����̂ł��傤�H
K�F���ꂪ�Ȃ��Ȃ���₱�����ĂˁB�w�����w��x�̜b�����Ă����ƁA�J������ܔN�ڂ�1935�N�܂ł�1930�N���N�_�ɂ��Ă���B1935�N�ɂ���Ă���̂��u�J�����N�L�O�u����v�m�ʐ^�P�n�B���ꂪ�ǂ������킯���A���N��1936�N�ɂ́u�J�ݑ攪�N�L�O�u����v�ɂȂ��Ă���m�ʐ^�Q�n�B
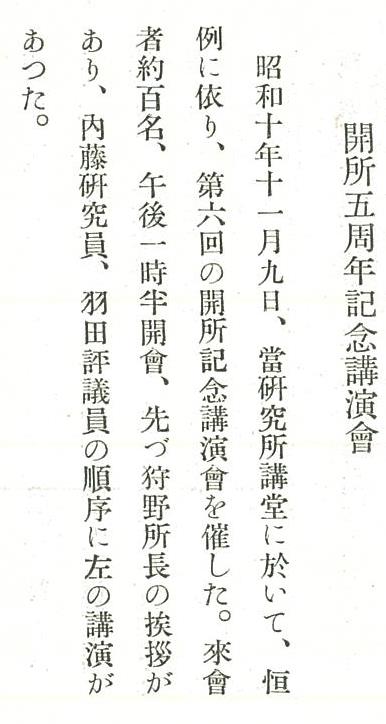
�ʐ^�P�@���a10�N�͊J���T���N�i1936.11�w�����w��x7�j
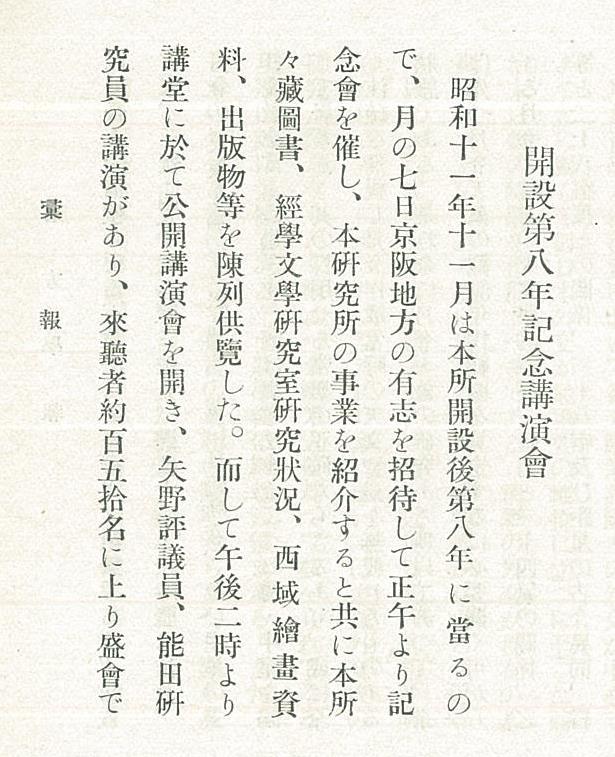
�ʐ^�Q�@���a11�N�͊J�ݑ�8�N�i1937.10�w�����w��x8�j
H�F�T�̎����W���Ė��炩�ɂ�����������Ȃ��ł����B
K�F�ǂ��l���Ă�����������ˁB1929�N�̐ݗ����琔���đ������W�N�ڂɂȂ邱�Ƃ͎���������ǁB�������A���������ύX�������N�����悤�Ȑ��x�I���҂����ɂȂ��B
H�F���������������ւ̉��g��1938�N�ł�����ˁB���ŕς�����̂����킩��Ȃ��킯���B�ŁA���̂܂܌��݂Ɏ���킯�ł����H
K�F���ꂪ�����ЂƂЂ˂肠���āB�s��̔N�͊J���L�O�s���Ȃ��B�܂��A�I���R�J���ł���ǂ���ł͂Ȃ������낤�B
H�F��������̂͂��ł��傤�H
K�F1946�N11���ɂ͍ĊJ�����B�ŁA�������̘b�ɖ߂��ƁA���̎��ɁA�u��\�����N�v�J���L�O�u���ɂȂ��Ă���B���������N�ł͂Ȃ��ݗ��N���琔����悤�ɂȂ�B�ł��J�Ì���11���B�����͕ς��Ȃ��B
H�F���̃h�^�o�^�ł����ƒ������A�Ƃ������ƂȂ�ł��ˁB
K�F�����A�n�������̂����ɑ���Ȃ�A���N�́u87���N�v�Ƃ�������B���̎��̐������Ȃ�u��89�N�v�Ƃ�������B���N�A�Ď����j���ėǂ��̂��ǂ����A�悭������Ȃ��Ȃ�ˁB�K���A����l�����ŕĎ��L�O�s�������悤�Ƃ����b���Ȃ������Ȃ̂ŁA�S�����Ȃ��̂�����ǁB
H�F�Ȃ�قǁB�Ȃ��Ȃ������[���b�ł͂���܂��ˁB�ł����A�A�ڂP�Ƃ��Ă̓}�j�A�b�N�����Ďア�̂ł́B
K�F�_���ł����B��͂�B
�����c�����Y�Ɓw�O���̏W�x
K�F�ł́A�u���c�����Y�Ɓw�O���̏W�x�\���m��J�����փX���o�\�v�Ȃ�Ă̂͂ǂ��ł��傤�H
H�F���c�i1924-2007�j�̐t����Ƃ������Ƃł����ˁB�ł��܂��ǂ����āw�O���̏W�x�H
K�F���܂��܌Ö{�Ŏ�ɓ����ĂˁB
H�F�w�O���̏W�x���ł����H
K�F����A���c�����Y�́w�O���̏W�x�i1941�j���B
H�F���H�@���H�@�{���ł����H
K�F�{���A�{���B���ɂ����Ɩ��O������B�ق�B�u�O�������@���c�����Y�v���ď����Ă���ł���m�ʐ^�R�n�B

�ʐ^�R�@���c�����Y�����@�O���̏W�i1941�j
H�F�Ȃ�ł܂�����ȃ��m���I
K�F�Ö{����̐��ʁB���Ȃ���Ƃ��[���Ǝv������B����ȃ��m�������̎�ɓ���̂��A�ƁB�����Ƃ������m�́A������ł������]�ގ҂̑O�Ɍ����ˁB
H�F�ǂ����̖��p�����Ⴀ�邢�܂����i��j�B����͂����Ƃ��āA�ł������̉̏W�ł���B�����ʔ������Ƃ������ł����H
K�F�������݂��ʔ����B
H�F�ق��A���Ƃ��H
K�F���Ƃ��A����ȉ́B
�f�J���V���̃w�o�Z���K�I�R��
�I�R���Z���m�q�K�̃E
�g�c�R�J����r���c���n
���n���f���V���惊
�O���O���g�����i�O��
�O���{��m���T�V
�{��{��g�����i�{��
�{��O���m�P�C�R��
���m��J�����փX���o
��m�h�a���E�K��ナ�m�ʐ^�S�n
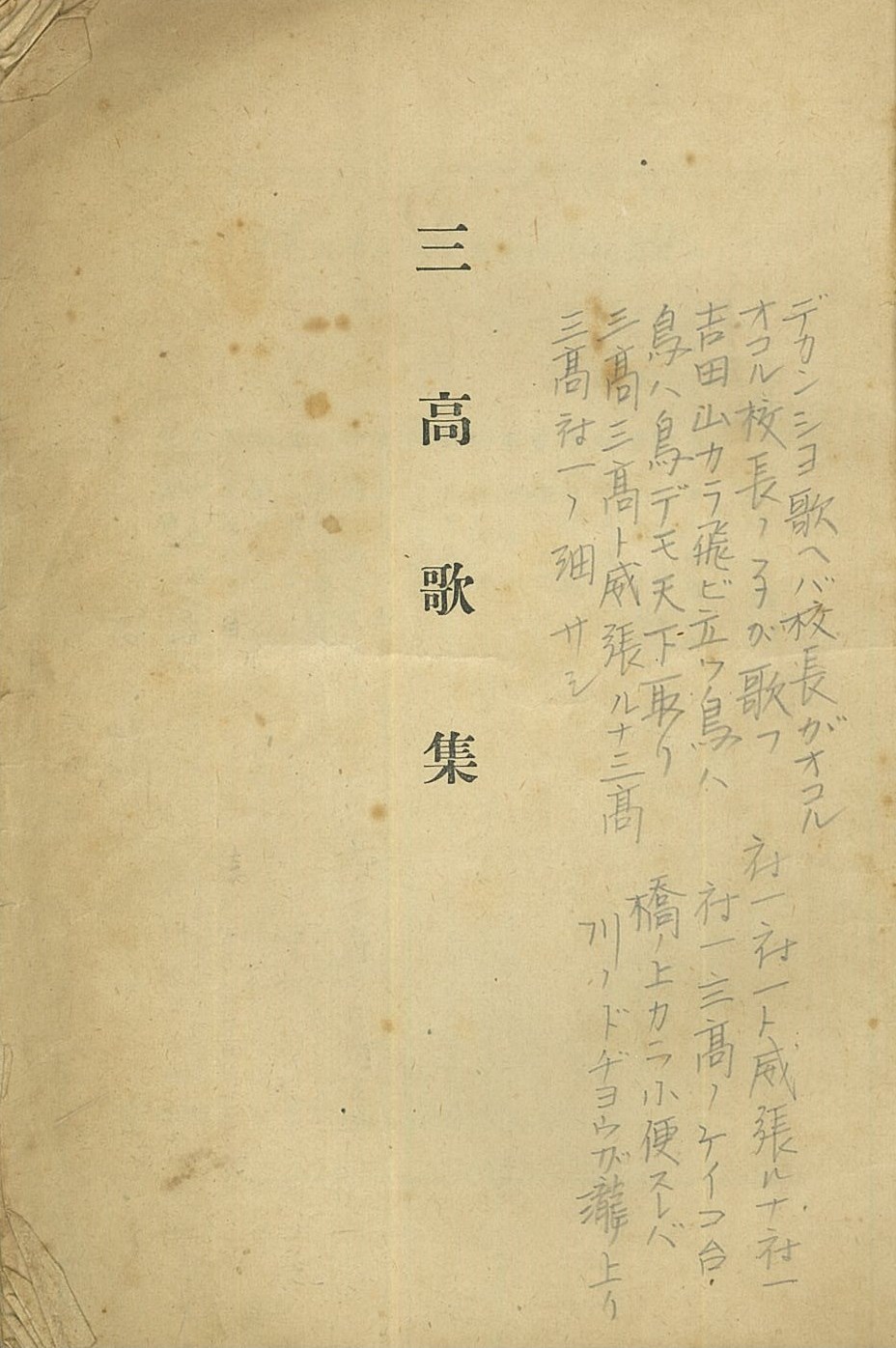
�ʐ^�S�@���c�����Y�����@�O���̏W�i1941�j
���c����������̂��A�������߂����̂��͕�����Ȃ����ǁA�����̗l�q��������ł���ˁB
H�F�������ɁB�A�ڂ̏��߂̂ق��ł��G���ꂽ�悤�Ɂm�A�ڑ�2���n�A�K���A�L�ˁA�����A�~���Ƃ������V���s�w�h�̖ʁX�́A�݂�ȕ{��i���s�{����ꒆ�w�Z�j→�O���i��O�����w�Z�j→����i���s�鍑��w�j�Ƃ����R�[�X�����ōs���킯�ł����A���̕{�ꐶ�A�O�����̊�㵂���G���[�g�ӎ����A�悭����Ă��܂��ˁB
K�F�u���m��J�����փX���o�v�Ƃ��������ɂ��j�q�Z�ȃt���[�Y���A����̍r�_���̂��Ƃ��Ǝv���Ɩ��킢�[���B�r�_���͋߉q�ʂ�^���������ɐi�Ƃ���ɂ�����{�ꂩ���ԋ߂����B
H�F�r�_���Ƃ����A�����юi���ʊw�r���ɋ��̏ォ��k�R�߂āu�k�R�͍߂Ȃ邩�ȁv�ƒQ���������ł��ˁB
K�F�����B�w�Z�T�{���ĎR�ɓo�肽���Ƃ����C�������u�k�R�̍߁v�ɓ]�����Ă��܂��Ƃ��낪�A�����������������ȓI�Ƃ��������w�I�ō����I�B
H�F�J�߂Ă���A���Ȃ��Ă���B����͂Ƃ������A�ʔ����A�����ă��A�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ޗ��ł��ˁB�ł����A����܂��A�ڈ�Ƃ��Ă͓���̂ł́B
K�F���[��B�c�O�B���܂���Ȃ��������i�j�B���̎�̌Ö{�l�^�͂ق��ɂ����낢�날�����ǁA�������Ō��������������o�����ƂɂȂ��Ă���B���łɂ����ƁA�Ö{�̕��C�ɒ��������o�Ă��Ȃ��āA���M�ɂ��x��𗈂��Ă���B
H�F�_������Ȃ��ł����I
K�F�_�����ˁB�����҂Ƃ��ĂƂ������A�l�Ƃ��Ă����Ȃ��Ǝv���B
�������̂悤�Ȃ���
H�F���낢��ƍs���l�܂��Ă�����悤�ł��̂ŁA�����ς��Ă݂܂��B�{�A�ڂ̎艞���Ƃ������������ǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���H
K�F���ꂪ�F�ڂ悭������Ȃ��I�@���̊ԁA�{�A�ڂɂ��ĂQ��قǐV���̎�ނ������A���ߐ[���F�l�����́u���{�ɂȂ��ł����H�v�ƕ����Ă����̂ŁA�܂�������U��ł͂Ȃ��Ǝv���̂�����ǁA�����A�u�V���s�w�h�v�Ƃ����e�[�}������̓Ǐ��l�ɂǂ̒��x�S��������Ă���̂��A���܂ЂƂ����ł����ɂ���B
H�F�ł��A�V���s�w�h���e�[�}�ɂ����V�����o�Ă��܂����ˁB�{�A�ڂ̒S���ҏW�҂Ƃ��Ă͏��Љ��Ő���z���ꂽ�Ƃ������A�搶���L�`���Ə����i�߂Ă���ꂽ�Ȃ����Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ɁA�Ɯx������v���Ȃ̂ł����B
K�F���^�N�V�߂̒x�M�ɂ��Ă͂��l�т̌��t���������܂���B�Ƃ͂����A�ޏ���������̂́A���p�������Ƃ����킯�ł��Ȃ������Ȃ̂ŁA���悤�͂���Ǝv���Ă���B�ŁA�����Ŏ��p�ɃG�b�W�����悤�Ƃ���ƁA����Ƀ}�j�A�b�N�ɂȂ��Ď�ԉɂ��������Ă��܂��A�Ƃ������z��……�B
H�F�u������A�x�߂����Ƃ����Ă�i�{�j�v�B
K�F���������ĉ������B�ߔN�A���m���l�̍Č��������낢��Ɛi�߂��Ă������A�w�K�����v�x�Ȃ�Ă����V�����o�Ă����������͂Ȃ��Ǝv���̂�����ǁA�Ȃ����o�Ȃ��B�K���Ŗׂ����͂��̏o�ŎЂ��������Șb���Ȃ��B
H�F�����Ȃ�p�̗��b�����Ȃ��ʼn������B����͂Ƃ������A�搶���Ȃ���Ȃ�ɂ��O�����Ɏ��g��ł�����Ƃ������Ƃ����͗������܂��B
K�F�ǎ҂̔����ɘb��߂��ƁA�A�ڂ��䉏�ɂȂ������Ƃ́A����������܂����B�O��i��17���j�́u�ؖk��ʎʐ^�v�_�ŐG�ꂽ���쐴��搶�̂�������ɂ��Ă������ł����A�ؖk��ʎЈ��̎q�킩��͑����̌䋳�������邱�ƂɂȂ�A������̃v���W�F�N�g�����������i�s���ł��B�����A�u�l�����T���v����ǂ�ǂ������Ă��܂��̂ł����B
H�F���[��B�S���ҏW�ғI�ɂ͊�Ԃׂ��������Ƃ���B
K�F�����҂Ƃ��Ă͊������Ƃ���ł��ˁB���ƁA�{�A�ڂŁw�k���삱�ǂ����y�L�x�����グ�����Ɓi��15���j���䉏�ɂȂ��āA���y�L�̒��҂̂���l�A���������Y�搶���炨�莆�Ղ����̂��A���肪�����䉏�ł����B�A�ڂł��G�ꂽ�ʂ�A���w�U�N���Ŗk����̒n���ɂ��ď������������N�́A���̌�A�{���ɒn���w�҂ɂȂ����킯�ł����A���̓����搶���A60�N�O�ɏ������w�k���삱�ǂ����y�L�x������������Ƃ̂��l���ŁA�ŋ߁A�k����͓I�ɒ�������Ă��āA�������X���ꏏ�����Ă��������Ă���܂��m�ʐ^�T�n�B

�ʐ^�T�@���여���T�����铡�������Y�搶
H�F�܂������䉏�ł��ˁB
K�F����B�w�k���삱�ǂ����y�L�x�ɂ��Ă͗F�l�����ƃg�[�N�C�x���g���J�Â��܂������i�Q�l�j�A�z���ȏ�ɑ傫�ȍL���肪����A������Ɛ��̎v�z�����j��Ɉʒu�t���Ȃ���ƍl���Ă���܂��B���̈�[�͋߁X���s�����\��ł��i�ٍe�u�������́q���ǂ����y�L�r�\��ˁE�哌���E�k����\�v��ˉp�u�ҁw�����̃��f�B�A�~�b�N�X�x�v���t�o�ŁA�f�ڗ\��j�B�����A���̃v���W�F�N�g���i�߂ΐi�ނقǁu�l�����T���v����͉��������Ă����܂��B
H�F���[��B�S���ҏW�ғI�ɂ̓r�~���[�ȂƂ���B
K�F�\����Ȃ��B�������C���Ƃ������A�D��S�̕����܂܂ɐi�݂����ق��Ȃ̂ŁB�܂��A����Ȃ���A�u�l�����T���v�ȂǂƂ������d�ȃe�[�}�Ɏ�����Ă��܂����킯�ł�����̂�����ǁB����Ȃ킯�ŁA�A�ڂւ̔����͂����₩�Ȃ��̂ł͂���܂����A����ɗE�C�Â����A�撣���Ă���Ƃ���ł��B
H�F�ǂ����̏��N���݂����ł����A�u�搶�ɗ�܂��̂��ւ���I�v�Ƃ������Ƃł��ˁB
���u�l�����T���v�̂��ꂩ��
H�F�Ƃ���ŁA���낻�덪�{�I�ȃc�b�R�~�Ɉڂ肽���Ǝv���̂ł����A���̘A�ځA���ꂩ��ǂ��W�J�����Ă���������ł��傤���H�@�����r�W�����͂���̂ł��傤���H
K�F�ɂ��Ƃ����˂��Ă��܂��ˁB�������D�G�ȕҏW�ҁI�@�������ɁA�ŏ��ɌK�����v�_���W���I�Ɏ��グ���̂͗ǂ��Ƃ��āA��������̖����Ԃ�Ƃ��������]�Ȑ܂Ԃ�͂������Ȃ��̂��Ƃ����C������B�v�搫�̌��@���w�E�����̂������Ȃ��Ǝv���܂��B��Ȃ���B�ł����A������肽�����Ƃ����ژ_���́A���͂��łɒ��Ă����ł���B
H�F�ق��A�ǂ̂悤�ȁH
K�F�ȑO�A�wkotoba�x13���i2013�N9���j�ɏ������u�V���s�w�h������l�����̃��j�[�N�����u�V���v����ǂ݉����v�̂Ȃ��ŁA�V���s�w�h�̃��j�[�N�l�X���A�@���������A�A�t�B�[���h���[�N�A�B���m�w�A�C��O�����_�A�D�v���O�}�e�B�Y���i���邢�͎������_�j��5�_�ɐ������Ă݂��B�Z���_�l�����ǁA�����}�Ƃ��Ă͂���ŗǂ��Ǝv���Ă��āA�������t�����Ă�����Ƃ��{�A�ڂƂ�������ł���B
H�F�Ȃ�قǁA�N���A�ŕ�����₷���I
K�F���Ȃ݂ɁA���̋L���ŏЉ���V���͎��̂T���B
�@�K�����v�ҁw���\�[�x�i1962�j
�A�����юi�w�l�ԈȑO�̎Љ�x�i1951�j
�B�O�D�B���E�g��K���Y�w�V�����I�x�i1952�j
�C�����G�r�w����������e���r�ցx�i1965�j
�D�~�����v�w�m�I���Y�̋Z�p�x�i1969�j
���ɈӐ}�����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���ʓI�ɑS����g�V���ɂȂ�܂����B
H�F�����[�����C���i�b�v�I�@�V���_�͋��A�ڂł����グ�Ă����܂������ˁi���A�ڑ�R���j�B�Ƃ����킯�ŁA����̓��t�����y���݂ł��I
K�F�����B���ꂪ�˂�……�B
H�F�܂������ڂɂȂ�Ȃ��ʼn������i�{�j�B
K�F�ۑ�̌��ʂ��͂��Ă���̂����ǁA�Ȃ��Ȃ������ǂ����Ȃ��B���Ƃ��A���߂���ؗE�ɔؗE���d�ˁA�����@���ڂ݂��ɑ����Ă���A�ڂł͂���̂�����ǁB����ɂ��Ă��A���m�w�v���p�[����Ȃ���蔖�Ƃ������A�ǂ����Ă������w�A�t�B�[���h���[�N�A���{�ߑ�j�Ƃ�������ɕ��Ă��܂��B�����A�䂪�g�̐�w��˂�I�グ����ɂ��Ă��A���{�̓��m�w�ɑ���Č����́A�I���G���^���Y���ᔻ�Ƃ������|�X�g�R���j�A����]�͂���ɂ͂���̂�����ǁA�ǂ����\�w�I�Ƃ������A���m�\���{�\���m�̎O�p�`���߂���}���I�Ȕᔻ�͊����ȒP�ɓ����o����Ԃ�A�w��I���H�̍����ɔ���悤�Ȏ��ؓI�ᔻ�͂�����ƂȂ���Ă��Ȃ��A�Ƃ�����ۂ������Ă��܂��B
H�F�������ɂ�����������܂���ˁB������Ƃ����āA�搶�������Ă������R�ɂ͂Ȃ�܂����B
K�F��������_�����i��j�B�L�`���ƓB���h���Ă���Ƃ��낪�������I�@�Ƃ͂����A���̕��ʂ͂ǂȂ��������̕��ɂ���Ă������������Ƃ����C�����̓n���p�Ȃ��ł��B
H�F��肩�������D�ł��̂ŁA�����g�őΏ����Ă��������B
K�F�d���Ȃ��ł��ˁB�܂��A���ΓI�Ɏ�𒅂��₷���Ƃ��납��A�������ׂ��Ă��������Ǝv���܂��B�x�X������݂ł͂���܂����A�O�͌����Ă���܂��B
H�F�d���Ȃ��ł��ˁB�ăX�^�[�g�A��낵�����肢���܂��B�l�I�ɂ́A�V���s�w�h�́u�ҏW�p�v�Ƃ����e�[�}���肪���Ă����������������ł��B
K�F�����B����͏d�v�ł���ˁB�����A�ڂ��ڂ��A���g�݂܂��B�Ƃ����킯�ŁA10�N��̘A��20�N�ɂ͍Ăсu�ˋ�ҏW��c�v���J�Â��܂��̂ŁA����܂ł�낵�����肢���܂��B
H�F�܂��Ђ��ς�C�ł����i���{�j�B
�i�I�j
|