No.1249(2020年11月号)
特集
No.1249(2020年11月号)
特集
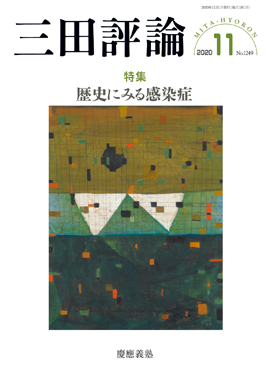
三田評論
2019年11月号表紙
学術会議が否定した「ホメオパシー」という民間療法がある。症状を引きおこすものを症状の治療に用いる方法である。本号座談会「シンパシー」(小川公代)という言葉に、「ホメオパシー」の発想を思い出した。コロナは人から人へとうつる。あくまで比喩で言うのだが、そこには感染ないし変種のシンパシー(接触、飛沫、空気、媒介)が働いている。一方、コロナ禍と戦う人たちが探り当てるのも、究極のシンパシー(同情、共感、共鳴、さらには親和力)なのである。本号はその総集編。病をおこすシンパシーではない。病を癒やすシンパシー。まず「丘の上」劈頭で「共感的自我」(生田久美子)が語られ、特集「歴史にみる感染症」では、まず文学(座談会)、ついで歴史(論文五本)の二企画で〈過去〉に事例が探られる。そして〈現在〉の心を見つめる精神科医による「特別鼎談」が辿りつく結論は、やはり「横のつながり」、すなわち「シンパシー」なのだ。
鷲見洋一

人類の歴史は感染症との闘いの歴史であったと言っても過言ではないでしょう。先人がどのように感染症と向き合ってきたのか。座談会「文学に現れる感染症」では、感染症がどのように人間の行動や内面に影響を及ぼしてきたのかを世界文学を例に語り合います。5本の関連記事では、日本史を中心に感染症に向き合ってきた人々の姿を浮き彫りにします。コロナ禍の現在、歴史を振り返ることで何が見えてくるでしょうか。
春先に緊急事態宣言が出て、はや半年以上が経過。この間、未知のウイルスに脅え、様々な不安に苛まれてきました。感染する/感染させる不安、人に会えない不安、経済的な不安、先が見えない不安……。精神科医、臨床心理士の方々による鼎談は、この「不安とともに生きる現在」の深層を洗い出し、日本社会の独特の構造をもあぶり出していきます。


大山エンリコイサムさん
アーティスト・塾員
インタビュアー:宮橋裕司(慶應義塾志木高等学校教諭)
ストリートアートの一つである「エアロゾルライティング」という手法で、主にニューヨークを拠点にアート活動を展開する大山さん。その原点は志木高校の卒業時に同校の壁に書いた「壁画」にありました。日本でも個展が次々と開かれ、気鋭のアーティストとして注目されている大山さんは、来春開館予定の慶應義塾ミュージアムコモンズ(KeMCo)にも作品を提供しています。原点から現在まで、その軌跡を辿るインタビューです。

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。
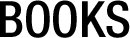 慶應義塾大学関連の書籍
慶應義塾大学関連の書籍