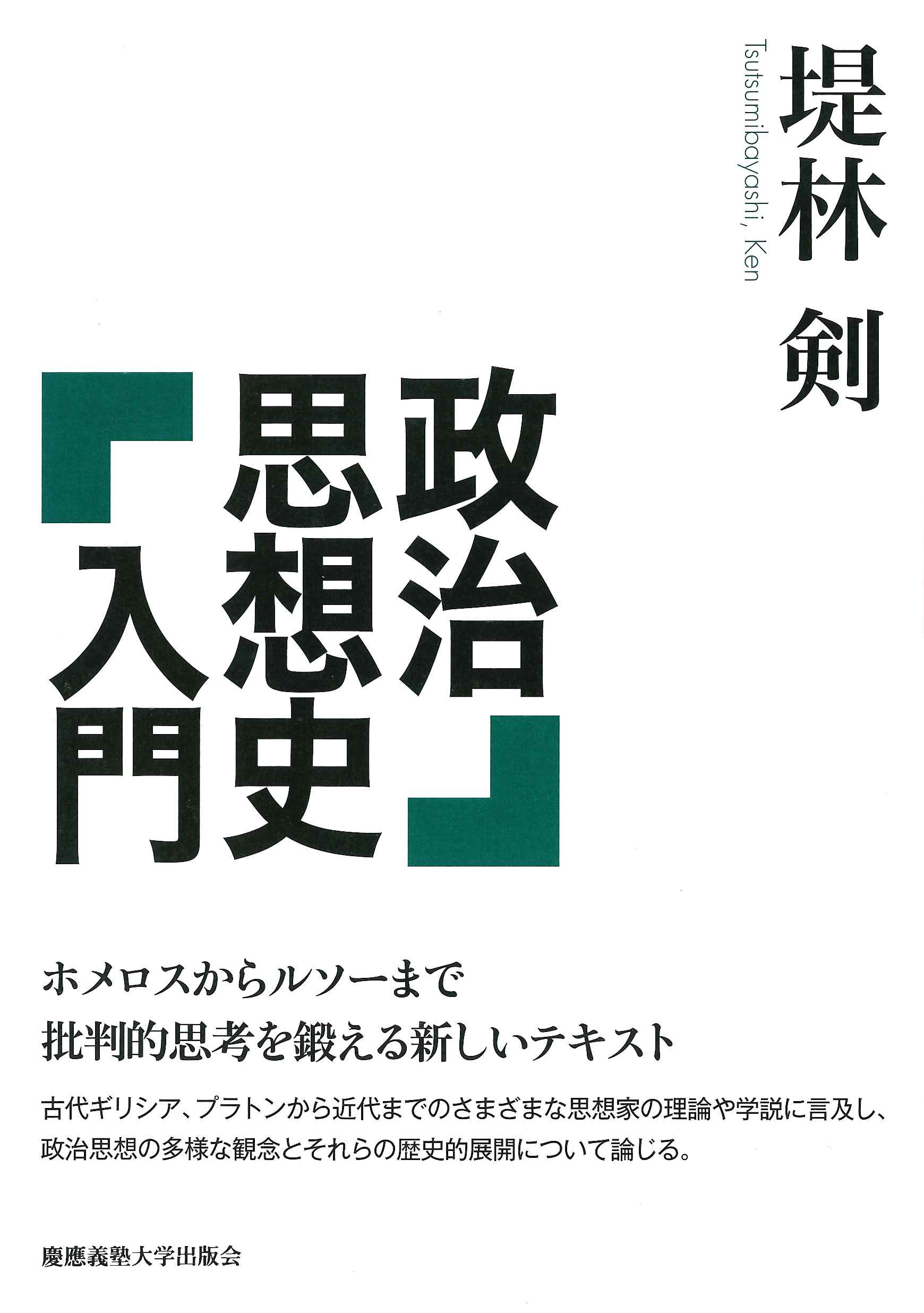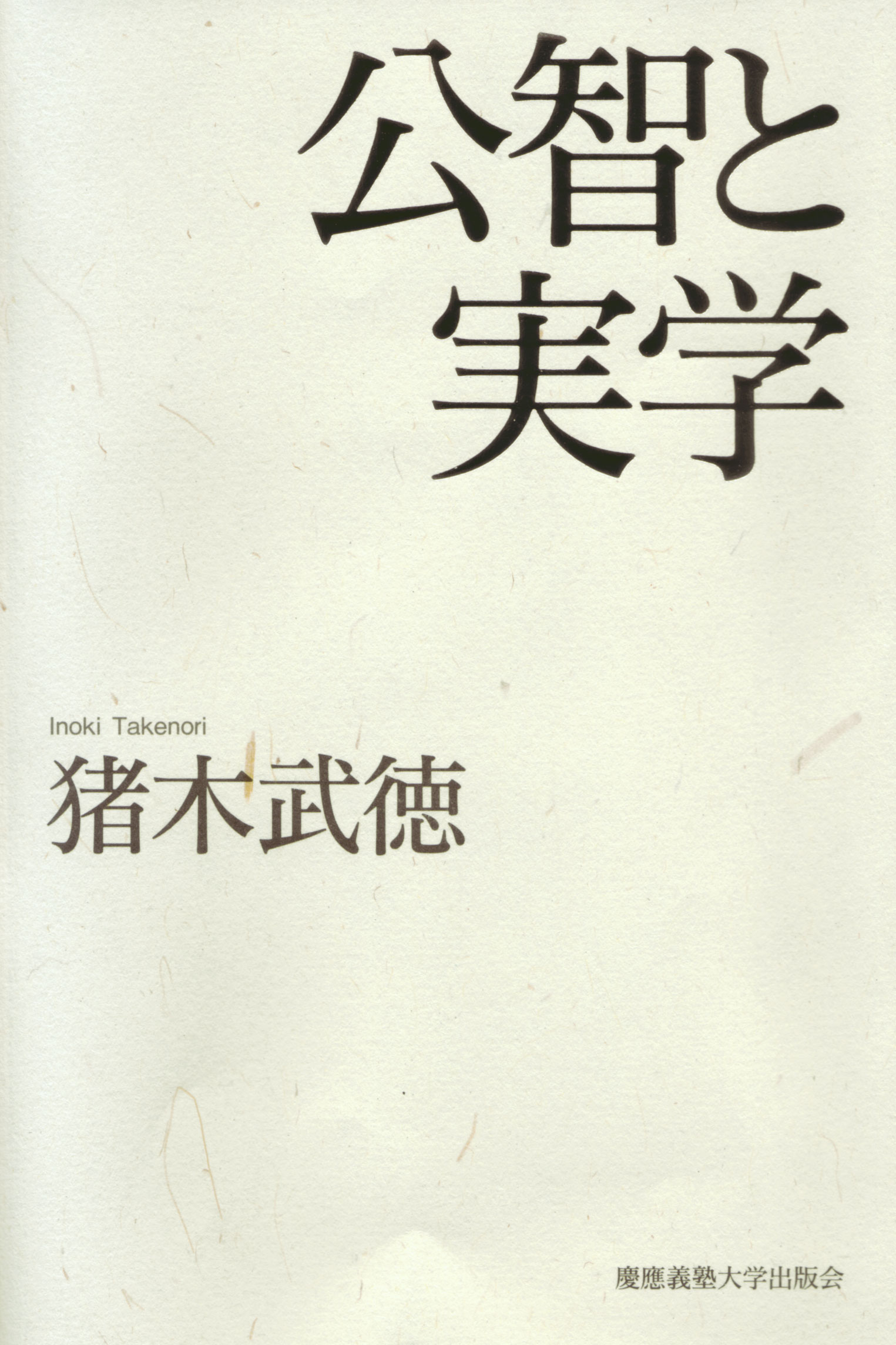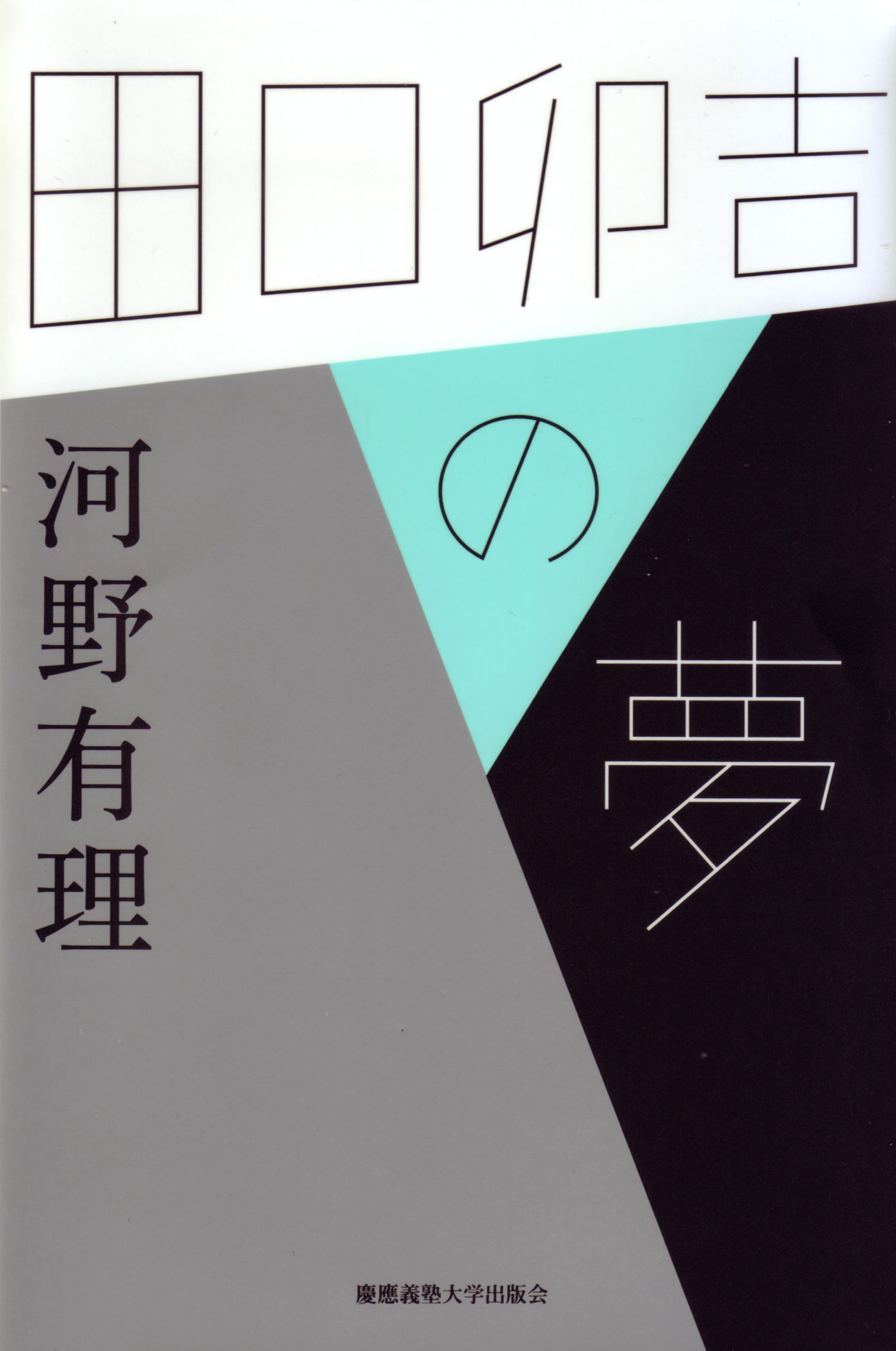■本書の「序」を抜粋して公開しました。ぜひ、ご覧ください。
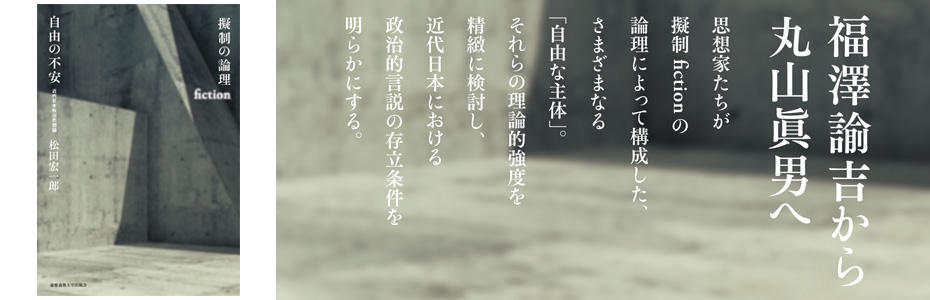
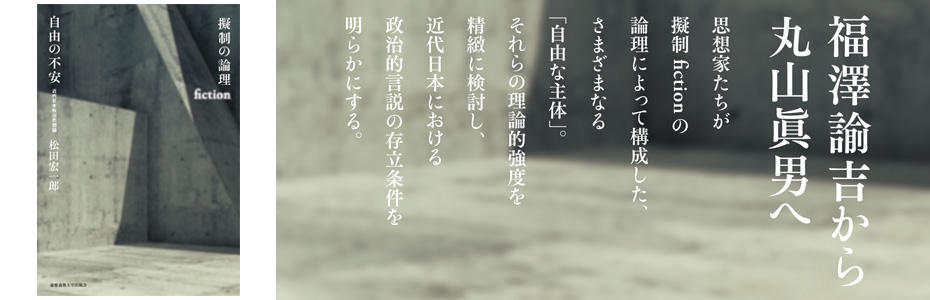
政治的「擬制」には、「日本国」、「国民」、「皇位」といった、まるで実体がどこかにあるような共同体的象徴も含まれる。「政治とは、人間の共存と共存象徴との間に存在する矛盾の解決にほかならない」という、岡義達の名言があるが、「共存象徴」が共同生活における実践と何の矛盾もないとか、矛盾はやがて完全に解決すると言い放つ者がいたら、かなり警戒してかからねばならない。また共同体こそが実体であり、たとえば個人の信条や良心や権利は「擬制」であるから、実体のために「擬制」は必要に応じて変更や廃棄可能である、と居直る権力が出現するかもしれない。これに対して、「個人」こそが実体であるといって争うのは、賢明な判断とはいえない。どちらが本当の実体かを争うのは無意味であって、そもそも「擬制」が実体に屈服しなければならない理性的な根拠は存在しないと抵抗するのが適切である(もちろん「個人」も「理性」も「擬制」である)。
「擬制」に対抗できるのは「擬制」だけだが、象徴形式にはそれぞれの社会的実践にふさわしいものとそうでもないものという意味での優劣があって、いずれも象徴形式であるとしても、「理性」は「神話」よりも優位に立たねばならないと主張するのが、政治(学)の然るべき役割である。ただし、こういった主張が、ほぼいつもどの社会でもあまり好まれないのは、特に政治学者でなくとも気がつく一般的現象である。
本書は、近代日本の政治思想の担い手が、新しい思考の技術ともいうべき「擬制」の力をどう認識したのか、その力による、「自由」や「自治」を「権利」として守り主張すべき主体(それが個人とは限らない)をどう理論的に構成したのかについて、必ずしも「自由」や「自治」を価値的に肯定しなかった論も含めて、分析・検討する。これは、後代の歴史研究者という特権的地点から、「擬制」の論理の出来具合や達成度如何を判定したり評価したりすることが目的ではない。たとえば、国家や社会による個人的あるいは集団的権利に対する侵害に、抵抗あるいは反撃するための言説と個人の自由の理念がたどった輝かしい道の検証ではない。権力ができるだけ都合良く恣意的に人々の権利を侵害することに役立つ「擬制」を生真面目に案出しようとする思想も、本書の検討対象に含まれる。もちろん、「自由」の悲惨な敗北への慨嘆でもない。権利主体はそもそも個人だけなのか、集団、あるいは国家でも主体たり得るのか、その場合相互の関係はどう説明できるのかといった問題について、それぞれの論者は個性的な見解を示しており、その間に深刻な対立や認識内容と概念使用法の相違があった。その対立と緊張自体が関心の対象である。
この現象は、やはり歴史的に特徴のあるものであった。たとえば、近世の「道」や「聖人」や「神洲」をめぐる論争と照らして、道具立てが一見新しくなっただけで、同じようなものであったと済ますことはできない。提出された議論の論立ての具体的様相を検討すると、多様、複雑かつ深度のある思考を見いだすことができるが、共通するのは、「共存象徴」の不安定さを自覚したがゆえの、戦闘意欲とおびえのないまぜになった態度である。
(松田 宏一郎)
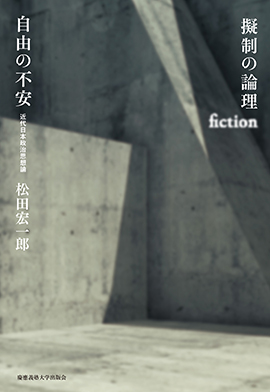
「擬制fiction」という思考の技術は、近代日本の政治思想の担い手たちに、自由、平等、あるいは自治を権利として主張し守る主体を理論的に構成する新たな途を開いた。するとそこには、彼らが生きたそれぞれの時代相に密接に関わるさまざまな思想と、それらのせめぎ合いとが生まれた。侵害されてはならない権利主体は個人か集団か国家か。政治的共同性を可能にする集団的な価値や感情をどのように捉え、あるいは構想するか。そして、そもそも人々は自由になるべきなのか。こうした問いへの、福澤諭吉、中江兆民から丸山眞男にいたる思想家たちの見解とそれら相互の対立を精査。自由な主体の共存という課題に、不安におびえつつ、しかし果敢に応えようとした彼らの、豊かな理論的成果だけではなく方法的な失敗や視野狭窄をも明らかにする。日本における、擬制の論理の達成と隘路とをともに描き出す、待望の論文集。
| 分野 | 人文書 哲学・思想全般 |
|---|---|
| 初版年月日 | 2016/06/23 |
| 本体価格 | 5,800円(+税) |
| 判型等 | A5判/上製/352頁 |
| ISBN | 978-4-7664-2353-2 |
| 書籍詳細 | 目次や詳細はこちら |
立教大学法学部教授。法学博士(東京都立大学)。日本政治思想史専攻。
1961年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学。
2008年、『江戸の知識から明治の政治へ』(ぺりかん社)でサントリー学芸賞(政治経済部門)。