No.1259(2021年10月号)
特集
No.1259(2021年10月号)
特集
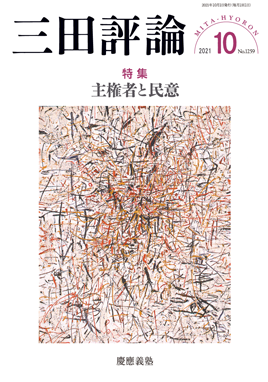
三田評論
2021年10月号表紙
重い特集。若年層の低投票率も心配だが、政治家への信頼と政治への期待回復の方が先ではないか。政治参加については中永廣樹と末木孝典の教育に期待。鈴木規子の分析にも多くのヒントが。執筆ノート4冊も社会の対立や利害を調整する政治の役割。「女子学生ルームができた頃」で、10年ほど前、理工学部女子学生のための就活講座を開催したことを思い出す。OECDの調査によれば、日本の理系女子学生数は36カ国中の最下位。女性教員も3割以下。理事と学部長に至っては…。演説館「性暴力から守る」。就活でもいまだによからぬことが。女性の筋力は男性の六割程度。心理学、脳科学、社会学、人類学など、あらゆる知識を総動員して、被害者も加害者もいない世の中に。まずは小笠原和美監修の絵本を孫に送ろう。三人閑談は「旅行記」。旅で違いと同じを知る。稲川琢磨は「日本酒を世界酒に」。シャンパン造りの仏達人も日本酒に魅せられ、逆に富山で酒造り。
(山崎信寿)

この秋には総選挙が行われます。2016年より選挙権年齢が18歳に引き下げられましたが、その後も若年層の投票率はかなり低調。政治的無関心の拡がりが危惧されています。日本の若年層が政治にかかわりたくないと思うのはなぜなのか? その背景は? 教育のあり方は? これからの政治参加、民主主義のあり方について、名うての論客が討議します。


稲川琢磨さん
株式会社WAKAZE代表取締役社長・塾員
インタビュアー:小尾晋之介(慶應義塾大学理工学部教授)
理工学部在学中に、ダブルディグリープログラムでフランスのエコール・サントラルに留学、その地で今、日本酒造りとその普及に奔走する稲川さん。「日本酒を世界酒に」をモットーにヨーロッパ市場の拡大を狙っています。日本において日本酒離れが言われる中、世界中の人に受け入れられる日本酒造りへの挑戦に注目です。

この1年半もの間、旅行に行けずに鬱屈した思いを抱える人も多いのでは? そんな時には過去の文人が記した雄大な「旅行記」の世界を垣間見てみませんか? イスラムの大旅行家、イブン・バットゥータやイギリスのデフォーやスウィフトなど、実録とフィクションが入り混じる「旅行記」の世界は、書斎にいるわれわれの想像力も刺激してやみません。人はなぜ旅をするのか。そんなことも考えさせる閑談です。

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。
会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。
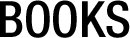 慶應義塾大学関連の書籍
慶應義塾大学関連の書籍