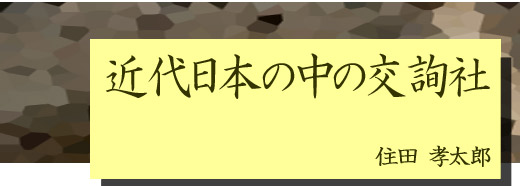
第6回 交詢社「緒言」−専門分化への危機意識
前回までに、小川武平の自立社、林金兵衛の自存社をはじめとして、自力社会の主眼である「私の仲裁によって、自ら治める」という意思が、交詢社創立の目的に強く関与していることをみてきた。「知識交換世務諮詢」という交詢社の社是はそれを象徴する言葉として採用された。この提唱に、いかに人々が共鳴したかは発会当時の社員数、構成にも顕著に現れている。社員数1767名。その内訳は在京者639名、地方在住者1128名。社員の主な職業は官吏371名、学者365名、商281名、農123名、工12名、華族21名、府県会議員15名であり、未詳579名。当時これだけの幅広い分野の人物が集まったのはなぜだろうか。前回では社是の「世務」に「当世の国家社会のためになすべき仕事」という意味と、「世の中のわずらい、日常世俗のこと、世事の繁雑」という2つの意味があったことを確認した。今回は「知識交換」についてみてみよう。
★交詢社の社則立案過程―明治12年後半
第4回でふれたように『交詢雑誌』第1号「創立略史」によると、交詢社の社則は明治12年9月2日から検討がはじまり、社則立案委員として小幡篤次郎、小泉信吉、馬場辰猪、阿部泰蔵、矢野文雄が当たった。2週間ほどで草案ができ、20日から4回の審議の後、30日に決定し、10月2日に副規則立案委員に阿部泰蔵、矢野文雄、馬場辰猪を選び、9日に社則の印刷ができて頒布した。副規則は12月6日から3回の草案審議を経て決定されたという。
現在遺されている社則版本は4種類あるという。古い順にあげてみよう。 所蔵者の名を冠した西村本といわれるものが2種類((1)西村本第1、(2)第2)。(3)慶応義塾図書館本・同塾史資料室本、そして(4)交詢社本。これらには構成と内容に若干の相違がある。前回ふれた「交詢社社則附言」が(2)西村本第2から登場し、(3)で「交詢社設立大意」と名を変えて巻頭に移された。また「追加」という発会前手続きを定めた項目も(2)から登場した。(4)にいたって新たに「副規則」が登場し、「交詢社設立之大意」「追加」「緒言」「交詢社社則」「副規則」という構成になった。版本と構成をわかりやすくまとめると以下のようになる。
(1)西村本第1
「緒言」「社則」
(2)西村本第2
「緒言」「社則」「交詢社社則附言」「追加」
(3)慶応義塾図書館本・同塾史資料室本
「交詢社設立之大意」「追加」「緒言」「交詢社社則」
(4)交詢社本
「交詢社設立之大意」「追加」「緒言」「交詢社社則」「副規則」
★知識交換―専門分化への危機意識
上記の社則立案の過程をみると、「緒言」が交詢社の設立意図を記した最初のものといえる。900字弱の短い文章であるが、現在が「分業に基づく時代である」ということからはじまっている。未開の時代には1人の人間がいくつもの職業を兼ねたり、1つの店が多くの品物を売っているものだが、時代が進むと人々に専門の務めができ、各家の生業ができる。分業と専門化が進むことで、職種の幅が広がって利益は大きくなり、そうなると一層分業化が進んでゆく。これが「現今世界の通勢」であるという。
しかし、人々が専門の仕事に従事するようになると専門外のことにうとくなるし、年齢や富の多寡、住む地方が異なれば人々の利害も異なる。こうなれば人々はうまく世をわたることがむずかしくなる。そこで、各業、各年齢、各地方の人を結んで互いの知識を交換し、補い合うことが現在に最も必要なことであるというようなことが、この「緒言」前半で分業社会への対処法として説かれている。
設立者たちが考えた専門分化についての危惧は、交詢社の社則立案委員の1人であった小幡篤次郎の「専門学校の切要を論ず」という講演にもみてとれる。専門学校の重要性を訴える小幡の講演のタイトルは、一見すると交詢社の「緒言」と一致しないようにもみえるが、交詢社に関連して興味深い内容を含んでいる。
★小幡篤次郎「専門学校の切要を論ず」−明治12年初夏
小幡は福沢諭吉とともに慶応義塾の創立に関わった人物の1人であり、彼が活躍した明治時代には一流の知識人として広く世に知られていた。福沢の事業の多くに尽力しただけでなく、「徳の人」として知られる小幡の言論活動は福沢の思想と密接に結びついており、彼の遺した論考は、福沢の思想、事業の展開を理解するしるべとなる。
ところで、明治12年1月、文部省の主導で「教育の事を議し、学術技芸を討論する所」(「東京学士会院規則大意」)として東京学士会院(現在の日本学士院の前身)が作られると、福沢とともに小幡も会員に選ばれた。専門学校についての彼の論説は明治12年5月ないし6月に行われた講演録で、約7千字弱の長さのものである。その眼目を示すと以下のようになる。
- 時代や国を問わず、教育の理想は完全無疵の聖人賢人を育てることにあるようだ。一身に知徳芸能を備えるのを願うのは世の希望であり、異議を挟む余地はない。しかし、「世の実況」をみると、これをやめて一芸一能の人を養成することをめざすべきである。
- そのために「博識」ではなく「深識」を主義とした教育を方針にするとよい。たとえば、医師養成に医学校を設けるように、米を植える者に米学校、桑を植える者には桑学校という各業種に即した学校をつくる。弟子奉公と学校とを併合させたようなものである。このように実用と理論が助け合う道を探れば、事業を進める識見を得られるし、伝統的な古い方法に固着する幣害を免れて、天下の事業が改まるだろう。
小幡がいう「世の実況」は次のようなものであった。100人中99人までが生きるために衣食の犠牲となって生涯を送り、一芸一能さえ修得する暇もない。逆に学校の教育を終えてみても「かえって至る所大概実用者(実務家)に道途(道)を閉じられ足を立るの地なければ、甚だしきは単純の力役に従事し厮養(しよう:雑役)の賎役を執るに至る者あり」という状況がある。一方、雇用者側は欲しい人材がなく事業を諦めざるを得ないと嘆く。雇用者と被雇用者の需給がかみ合っていない現状を小幡は深刻に見ていた。
さらに人材の需給関係の不一致に留まらない時代状況を彼は力説する。現在の我が国は未曾有の大変革に遭遇している。封建世禄がなくなって士族が資産を失うのみならず、農工商も同様に変化の激しい世に翻弄されている。こうした人々の教育に特別の注意を払う必要があるという。これらをふまえて、彼は上記眼目のように「弟子奉公と学校とを併合させた」専門教育を主張したのだった。
当時の教育制度下の専門学校は「外国教師にて教授する高尚なる学校(法学校理学校諸芸学校)」(明治6年、学制2編追加、第190章)であり、外国語の修得が必須とされていた。小幡の主張は雇用の需給関係の実態を観察し、「高尚」な専門教育からそれ以前の中学扱いの「生業の間学業を授け」「生業を導かんが為め専らその業を授く」という諸民学校や農業、通弁、商業、工業学校のあり方に近い「専門学校」(明治5年、学制第32-37章)を考えていたように思われる。
こうした小幡の問題意識のあり方とあいまって、満を持したかたちで交詢社の「世務諮詢」が登場したように思われるが、特に最後の部分は交詢社に絡んで見逃せない内容を含んでいる。
「人あるいは言はん、教育を取って専門に帰するは良好なりと雖も、之がため社会の結構(構造)を片砕し、人世の結合に大害を生ずるあらんと。これまた大に恐るべき幣害なり。然れども、あるいは二三の学科書は万科に通じて必読せしむるの方法あるべし。又異科殊業の人と親戚朋友となりて交際するもあるべし。又やむを得ず利害得失を他業の人と共同するもあるべければ、必ずしもこれが為社会の結合を片砕するの恐れあるべからず」
彼は専門学校ができると人々が分化し、社会がばらばらになってしまうのではないかという反論を想定し、対処策としてあらゆる分野に通じる書2、3冊を読ませること、業を異にする人たちとの交際を挙げている。こうしてみると、小幡は交詢社「緒言」に記された専門化への危険を自覚したうえで、専門学校の必要を説いていたことがわかる。さらには対処法として「異科殊業の人と親戚朋友と為りて交際」「利害得失を他業の人と共同」することを述べた内容が、いよいよ交詢社となって具体化されることになったように思われるのである。発会時の社員の職業構成が多様だったことからも分かるように、交詢社の構想の背景には人々が専門分化してしまうことで人々のむすびつきが崩れるという危機意識が強くあったのだろう。この「社会の結合」が交詢社の重要な眼目でもあったのだが、それについては機会を改めて。
【出典】
交詢社「創立略史」 |
|
『交詢雑誌』第1号、明治13年 |
|
交詢社社則版本 |
|
| 『交詢社百年史』(交詢社、1983年)、17-20頁 | |
| 交詢社「緒言」 | |
| 『交詢社百年史』、24頁 | |
| 小幡篤次郎「専門学校の切要を論ず」 | |
| 『東京学士会院雑誌』第1編、第5冊、また日本近代思想大系10『学問と知識人』(岩波書店、1988年)にも所収 | |
| 「東京学士会院規則大意」 | |
| 『日本学士院八十年史』(日本学士院、1962年)、67頁 | |
| 学制 | |
| 『学制百年史』(文部省、1972年)、資料編、15頁および24頁 | |