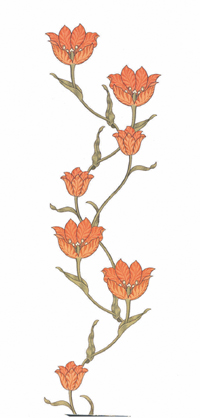アメリカの東海岸から西海岸にわたる数々の大学で調査を行い、原稿を執筆し、どんどんと発展するアイディアを基に講演を行っている間、かつては普通の人びともシェイクスピアやオペラ、そのほかこんにちでは「ハイブラウ」と分類されるような文化形態を享受していたのだと主張すると、しばしば聴衆が不快感を抱き、時には敵意さえ抱いていることに気づいた。アメリカでは十九世紀の大半を通じて、シェイクスピア劇とベルカント・オペラはポピュラー・カルチャーの一部であったという意見は、ある人にとってはあまりに耳新しいゆえに簡単には容認できない概念であり、またある人にとっては彼らの文化ヒエラルキー観をひどく脅かすものだったのだ。
しかしながら、ひとたび一九八八年に『ハイブラウ/ロウブラウ』が出版されると、もちろんこのような意見も出たが、それらは少数派に終わり、書評者たちは私が提示した主張に賛同を示してくれた。より重要なことに、本書は多くの大学の授業で採り上げられ、また読者も歴史専門家に止まらなかった。私は劇場や歌劇団、交響楽団、美術館といった芸術団体から頻繁に招待され講演している。こうした事象そのものが、本書の「おわりに」で論じた変化の確証となるだろう。すなわち、十九世紀の転換期に創られたヒエラルキーの基準はもはや絶対ではないということだ。
シェイクスピアと彼の作品は、高等教育機関に通う多数の若者たちを対象にした授業を通じて、再び多くのアメリカ人にとって馴染み深いものとなった。シェイクスピア劇の映画を観ることとそれらを読むことのつながりは、『ロミオとジュリエット』や『リチャード三世』、『ハムレット』といった作品の映画が公開されると原作の売り上げが二倍にも三倍にも膨れる事実から明らかである。(5)劇団は、十九世紀同様に、主要都市から遠く離れた土地へも繰り出している。シェイクスピアの演出家ジョエル・ヤンケは、モンタナ州の小さな町バーニーで、六年前に観たマルヴォーリオ[『十二夜』に登場する執事の名]と最近観た同役を比べて論じる、大きなカウボーイ・ハットをかぶった牧場主たちに出会った思い出を語る。(6)今一度、シェイクスピアは彼とはおよそかけ離れた事象を報じるニュース記事でも引用されている。たとえば、ボウリングの技の進歩に関する記事には「ハムレットがヨリックの骸骨を精査するごとく、技術者はボウリングの球を精査した」という一節が見受けられる。(7)さらに十九世紀と同じように、シェイクスピアは単なる大昔の人ではなく、こんにちに通ずる声の持ち主であった。二〇〇三―二〇〇四年の演劇シーズンにニューヨーク、ロサンジェルス、アトランタ、その他もろもろの地で、シェイクスピアの『ヘンリー五世』が突如として次々と上演された。ロサンジェルス女性シェイクスピア・カンパニーの監督リサ・ウォルプは、不良青年のハル王子が今までの人生を悔い改めて父王を継ぐ姿と大統領ジョージ・W・ブッシュの類似を公言する。「我々はイラク戦争に対して抗議活動を行い……『ヘンリー五世』の上演には意味があるように思えたのです。軍役をさぼり、プレイボーイで酒飲みだった若い頃のジョージ・W・ブッシュが長じて保守的な軍隊司令官となり、死者をも含む甚大な損害を両国に与えることも厭わずに父親が成し得なかった事業を追い求める、その姿に注目しました。」ワシントン・シェイクスピア・シアター劇団の監督マイケル・カーンによれば、ジョージ・W・ブッシュ政権下でハル王子の功績の物語を観る現代のアメリカ人観客は「若気の放蕩にふけった青年がやがて父親を引き継ぐ物語を興味深い」と思うに違いなかった。(8)
オーケストラ奏者たちは次第に、十九世紀最後の数十年に現れた、やる気のない演奏家を上から支配する独裁的な「天才型」指揮者に我慢しなくなっていった。「メトロポリタン・オペラのジェイムズ・レヴァイン、サンフランシスコ交響楽団のマイケル・ティルソン・トマス、ロサンジェルス・フィルハーモニックのエサ・ペッカ・サロネンのような指揮者たちは皆、演奏家をプロの同僚として遇し、なおかつ音楽的完璧さを達成することが可能であると示した」と、二〇〇二年に『ニューヨーク・タイムズ』の音楽評論家は述べた。(9)「真面目な」音楽の概念も拡張し続けており、ジャズはニューヨークのカーネギー・ホールとリンカーン・センター、ワシントンD.C.のケネディ・センターにおける主要演目と化した。二〇〇四年六月、ピューリツァー賞の執行委員会は「重要な価値を有する傑出した音楽作品」を構成するものの定義は「真面目な音楽を幅広く捉える見解」を反映する方向で見直され、以前は認めらなかったジャズやミュージカル、映画音楽の作品も含むようになったと告知した。(10)同様に、「クラシックの」なる単語自体も旧来のヨーロッパ中心主義的な意味合いから、インド楽器シタールによる音楽やハンガリー・ジプシーの歌、アメリカ・インディアンの舞踏、ケルト族やケージャンのヴァイオリン弾き、アフリカの木琴といった楽器や音楽ジャンルを包括するものへと変わりつつある。(11)
現在進行中の文化的変化を簡単に追ってきた。最後に、美術館もまた、ますます多様化する大衆に門戸を開放するようになり、その過程で美術の概念自体をより幅広く考えるようになっていった。一九九七年、アーノルド・L・リーマンはブルックリン美術館館長となった際に、美術館をより多くの人びと、とりわけ今まで歓迎されてこなかった少数民族の人びとにとって親しみあるものにしたいと宣言した。「美術館は人の人生を変え得るというメッセージを広めたいのです。」そのために、彼はさまざまな形式のポピュラー・カルチャーを展示して、来館者数の三倍増を目指した。彫刻の庭園を造って、美術館に一度も足を踏み入れたことのない人を惹き付けた。毎月第一日曜日には夜十一時まで開館して、ダンスをしたり、古いサイレント映画を観たり、食事と飲み物を楽しめるようにした。リーマンはブルックリン美術館を「イベントを楽しむ場所、実際に足を運ぶ場所――芸術そのものだけのためではなく――、自分たちのコミュニティを祝うために来るような場所」にしたかった。『ニューヨーク・タイムズ』の記事にあるように、そうすれば結局は「人びとは芸術を受け入れ、そのためにもやって来るようになる」と彼は確信していた。(12)
もちろん、文化のジャンルを取り巻き、その間を隔てる壁がなくなりつつあるとはいえ、旧来の姿勢は生き残っている。まさに本書の「おわりに」とこの「日本語版への序文」で解説したような変化そのものが反撃を誘発してきた。たとえば、批評家エイダ・ルイーズ・ハックスタブルやその他の人達は、美術館に併設された売店で美術品のレプリカを売ることは教育を促進するよりも、むしろ芸術を平均化し侮辱する行為だと主張する。「コンピュータの力によってスクリーン上の映像がオリジナルの美術品に取って代わり」、現実よりも幻影が好まれる事態となる。(13)「高尚芸術は個人のヴィジョンに関するものであり、ポップ・アートは……決まり切った形式に関するものであって」、この二つを混ぜ合わせては芸術を貶めてしまう、とニュージャージーのある新聞は論じた。(14)ジャンルのみならず展示場所の混同も非難される。二〇〇一年、コメディアン兼俳優のスティーヴ・マーティンはピカソ数点とスーラ、エドワード・ホッパー、デ・クーニング、デイヴィッド・ホックニーらの作品を含む美術コレクションの一部を、ラスベガスにあるベラッジオ・ホテル内にある、スロット・マシーンとギャンブル・テーブルの隣に設けられたベラッジオ美術ギャラリーに展示した。美術評論家グレース・グリュックはこの状態を「美術とカジノの結合」と呼んで弾劾した。「真面目な美術は騒々しいホテル……あるいはギャンブラーの二の次とされるようないかなる環境にも相応しくない。」(15)
かくして論争は続き、恐らくこの先も決して決着しないだろう。ただし、時代とともに姿勢は移り、文化的対立のバランスも変わる。今皆さんが手に取っておられる本書において、私は十九世紀初頭から二〇世紀初頭までのアメリカ人の文化に対する姿勢を辿ろうと試みた。これらの姿勢は決して確固たるものではなく、その変容を理解することによって、アメリカ社会とアメリカ人自身について一層深い理解を得られるだろう。
この序文を終える前に、本書に対して繰り返し向けられてきた批判について触れたい。それは私が「全員が一つの文化を共有していたと思われる、一八三〇年代か四〇年代より以前の合衆国の黄金期のようなもの」を想定しているとの批判である。(16)もし不注意にもかくなる印象を与えてしまったとしたら、ここで、私は「黄金期」があったと信じたことはなく、またそれを創り出す意図もなかったと述べさせて頂きたい。二〇世紀の大半を支配した厳格な文化ヒエラルキーは過去に存在しなかったし、未来にも必ずしも存続するとは限らないという点をこそ、私は本書で明示し得たと信じている。
二〇〇五年二月
ローレンス・W・レヴィーン
日本語版への序文
1. New York Times, March 17, 2002, September 2, 2004.
2. New York Times, April 28, 2002.
3. San Francisco Chronicle, February 8, 2005.
4. New York Times, November 18, 2002.
5. New York Times, April 22, 1997
6. New York Times, July 18, 2004.
7. New York Times, April 21, 2000.
8. Washington Post, January 4, 2004.
9. New York Times, April 28, 2002.
10. New York Times, July 2, 1996, June 1, 2004.
11. New York Times, September 4, 1997.
12. New York Times, March 17, 1997, April 24, 1997, April 12, 2004.
13. New York Times, March 30, 1997.
14. The Sunday Record, July 14, 1996.
15. New York Times, April 24, 2001.
16. Janice A. Radway, A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-Class Desire (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997), 366, note 4.