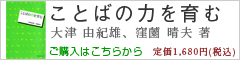実 践 例
本書を授業で活用いただいている学校の取り組みを紹介していきます。
報告者:中高英語塾講師 岡田順子
| 4. | 授業を振り返って | 「have には、“もつ”“飼う”“いる”“たべる”という意味があります。 覚えましょう。例文も書くからノートに書いてね」という授業スタイルよりも、 また、「have の多義性を英和辞書で調べてみましょう」というやり方よりも、 英語が苦手な生徒には母語である日本語から、haveの多義性を気付かせたほうが、こどもたちの頭に残ったように思う。 母語から入ることで、敷居が低くなり、こどもたちの「また、英語の授業か」みたいなため息は授業が進むにつれて消えていった。 英和辞書をひくより、和英辞書を引くほうが、やはり敷居が低く、辞書の数がペアでひとつずつだったことが返って幸いし、協同作業で熱心に取り組む姿が見られた。 |
|||
| 「多義語」その2へ戻る <-| | |||||